
2015年12月28日「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」が発表されました。今回は、このガイドラインについて解説していきます。
サイバーセキュリティ経営ガイドラインとは
このガイドライン、情報セキュリティ関連のものとしては、個人情報やマイナンバーのように罰則はありませんので、まだ盛り上がっていないようですが、かなり重要な意味があります。それは、サイバーセキュリティ対策を「経営責任」として位置づけたことです。
サイバーセキュリティ対策は「経営責任」である
今までは情報セキュリティ分野は、社内でもシステムに詳しい者に任せきり、というケースが多く見られ、世間でもそれがなんとなく当たり前のような雰囲気がありました。
しかし、このガイドラインが発表されたことにより、経営者がサイバーセキュリティ対策のリーダーシップを取り、その姿勢を平時より証明する必要が出てきたのです。「システム関係はわからない」「担当者に任せていた」は通らなくなりました。
経営責任が明記されたということは、もしサイバーセキュリティ対策が甘い状態で情報漏えいが発生すると、株主代表訴訟の理由にも成り得るということです。
確実な防止方法の存在しないサイバー攻撃
年金機構や昨今の攻撃事例に見るように、標的型攻撃やランサムウェアなど、システムセキュリティの知識が多少あったとしても避けられない事件は、多数発生しています。
攻撃者側は、メールに悪意のあるファイルを添付して送るだけですから、手間もかかりません。犯罪者にとってサイバー攻撃は、ローリスクハイリターンなのです。これからもどんどん送信するでしょうし、これからも攻撃件数は増え続けるでしょう。
皆さんの企業が感染・漏えいしていないのは、“たまたま”と考えなくてはいけません。感染・漏えいしないことが第一ですが、確実に守り切るということは不可能な時代になっているのです。実際に年金機構の事件を受けて、公的機関が模擬攻撃テストを実施したところ、添付ファイルの開封率は20%近くに上ったとの話もあります。
企業が生き残るために必要なこと
このような状況で、自分の身を守るためには、事件が起きたときに「やれることはやっていた」と対外的に認識してもらうことが重要です。「運が悪かった」「同じことやられたら、ウチでも感染するよな」と思われれば、多少のバッシングはあるにせよ、企業が生き残ることは可能でしょう。
ですが最低限、国から出されたガイドラインは認識し対応していた、と言えないと、株主や顧客など、企業の利害関係者は納得しないでしょう。だからこそ、早急に「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」の内容を認識し、対応しなければならないのです。
そしてこれは我が国の「サイバーセキュリティ戦略」の中で、企業選別に至るような重要な位置づけを持っています。
次回は、このガイドラインへの認識が一気に変わるターニングポイントになるであろう「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第三次行動計画の見直しについて解説いたします。







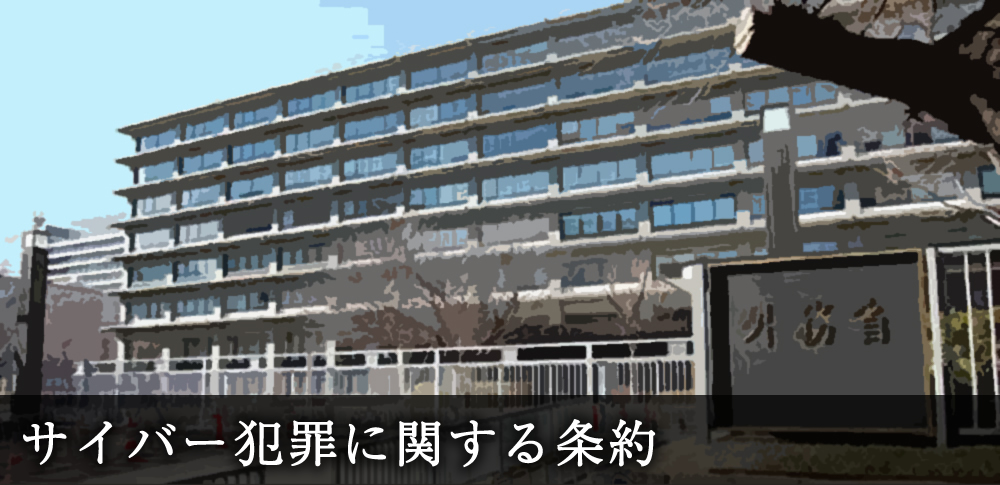
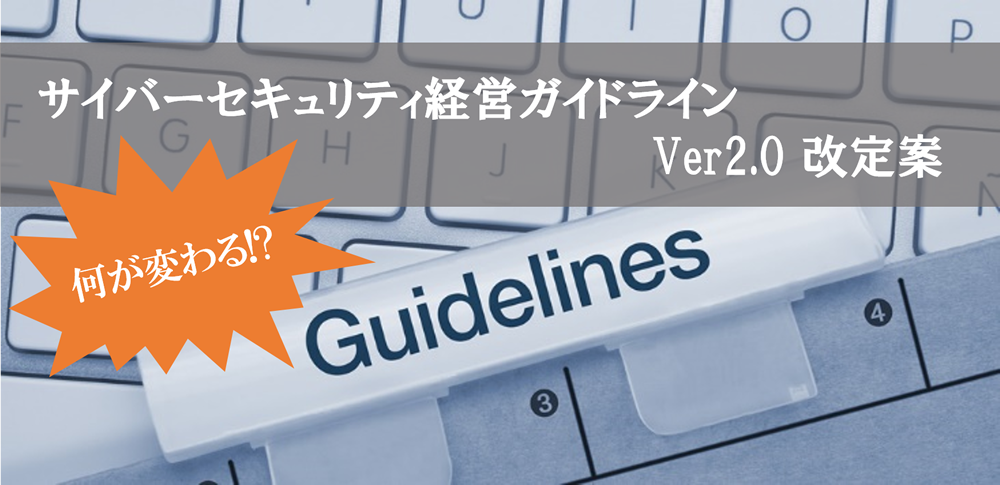





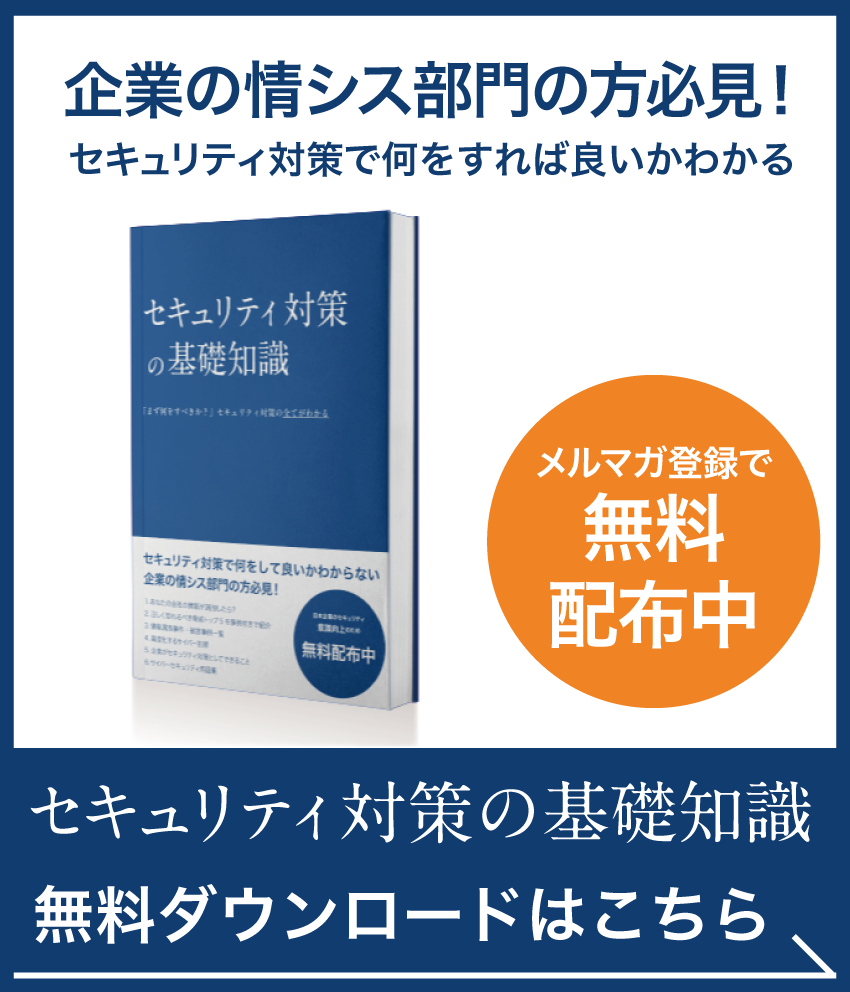
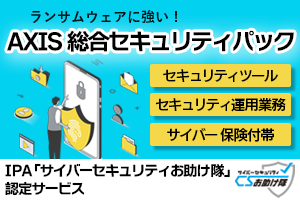
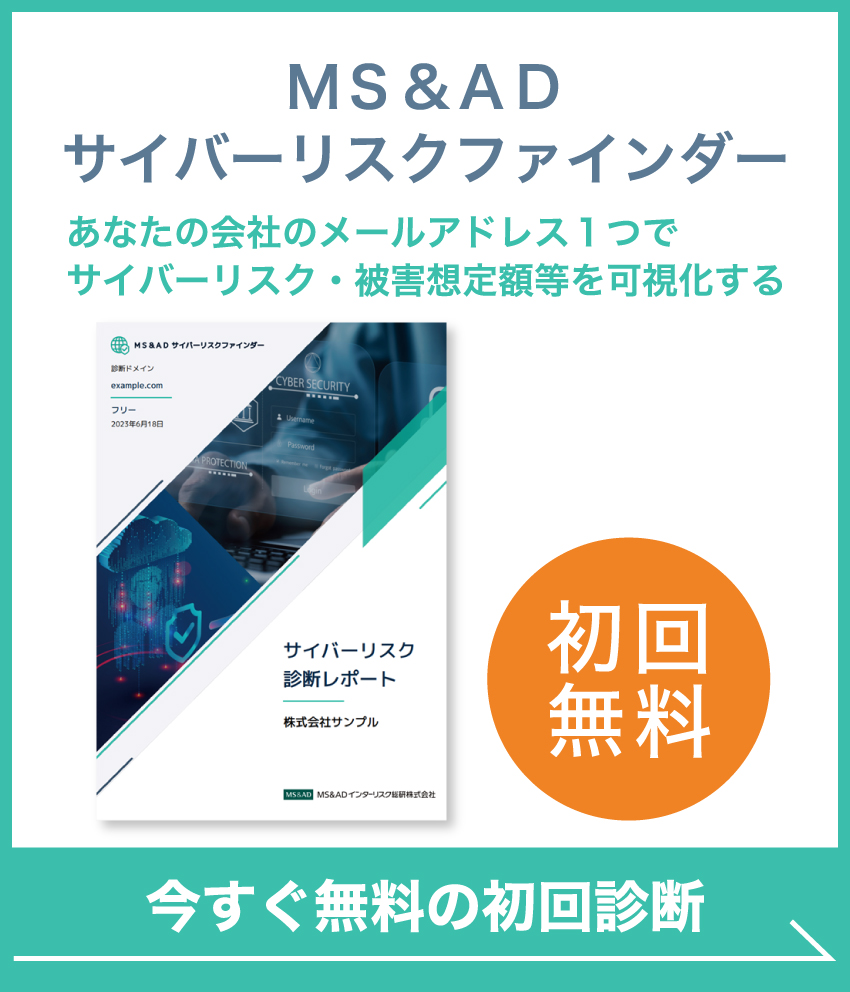
















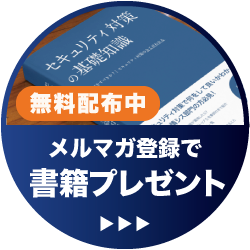
![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)


