
画像:総務省Facebookより
総務省は、IoT機器に求められるセキュリティ基準を満たすため、公的認証マークを付与する制度を導入する考えを打ち出しました。同省によると、2018年度中にも制度の骨子を整えることで、実現に向けるとのこと。
爆発的な市場拡大が見込まれているIoT機器に対して、安全的な信頼感を強化することで、一般消費の加速を見込む考えです。
増加の一途を辿るIoT機器への不正アクセス
総務省のこうした動きの背景には、IoT機器の浸透に伴う不正アクセスの増加という事情が存在します。
情報通信研究機構(NICT)によると、IoT機器を狙った不正アクセスの総パケット数はなんと約781億。2015年と比較して、IoT機器に対する攻撃は約5.8倍にも上っています。
また、2017年も「Satori」及びその後継となるIoTマルウェア「Mirai」が登場。IoT機器に求められるサイバーセキュリティーの基準は、確実に高くなっています。
認証マークのメリットとデメリット
総務省によると、導入を予定している認証マークの具体的な付与方法は、今後検討を進めて行くとのこと。業界団体や第三者機関による認定法はもちろん、メーカーの自主チェックに任せる方法まで、幅広い視野をもって議論する予定です。
これに対して業界団体にあたる情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)は、粗悪な製品を排除する意味から有効であるとメリットを認めつつ、コスト増による競争力の低下などデメリットについても危惧を示しています。






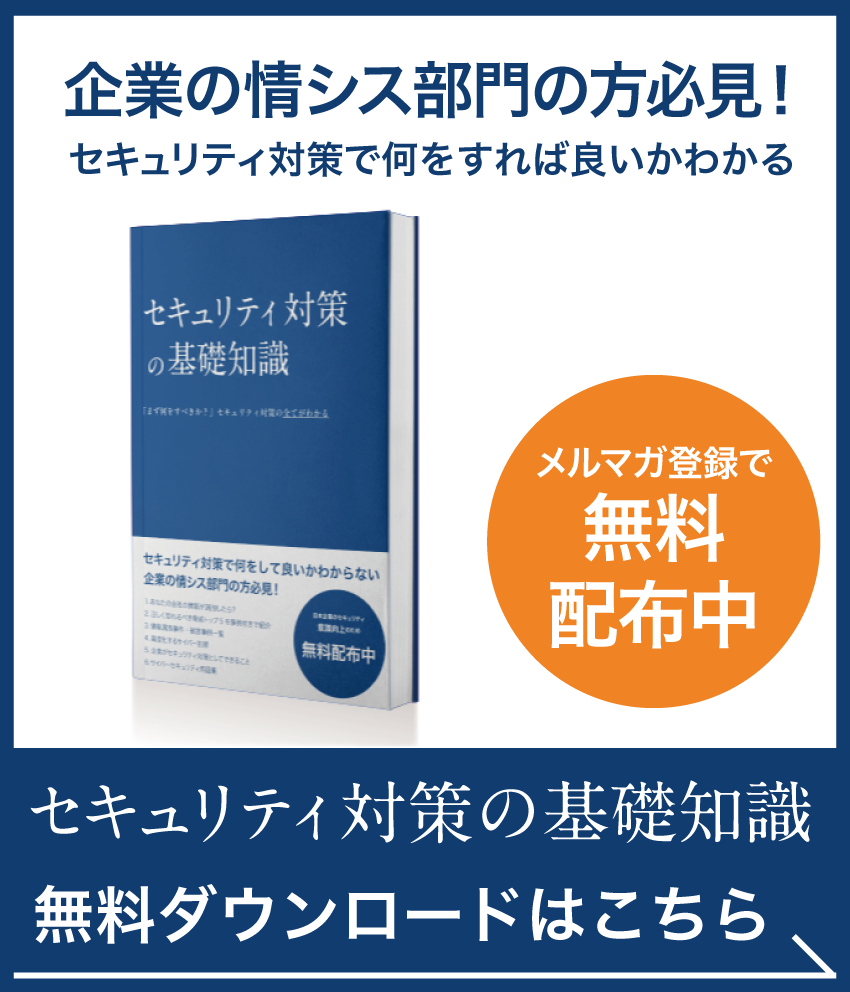
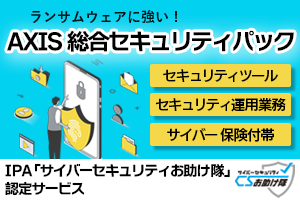
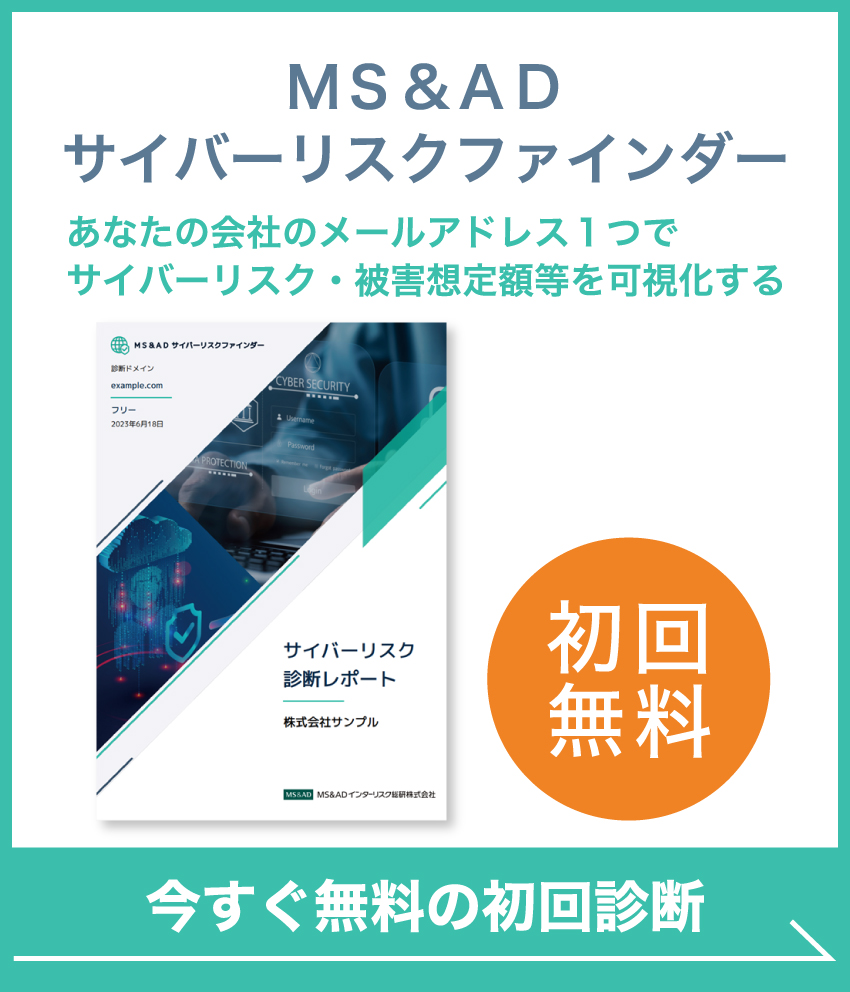

















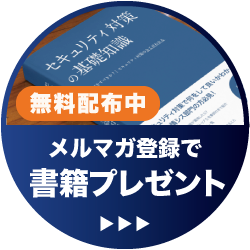
![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)


