
画像:大阪医科大学より
大阪医科大学で、患者のカルテ46万件が流出する事案が起きました。
報道メディアによると、流出させたのは同大学に所属する男子学生(24)。学生が講義データなどの収集を目的に教員用のPCにUSBメモリを使用したところ、メモリ内に保存されていた「バックアップソフト」が患者データなども自動転送。講義データだけでなく、レジュメデータや合計46万件の患者カルテが流出していたことが明らかになりました。
事案の経緯は?
大学及び報道メディアによると、男子学生は2018年1月25日頃からUSBメモリを使用。大学所有のPC上で「バックアップソフト」のインストールを行い、数分で作業を完了。講義が終わった後に学生向けのPCルームに移動し、サーバーから授業で使用したスライドデータなどを入手し、持ち帰っていたとのことです。
大学側は異常に気付いたのは2018年4月11日。一度はサーバーのデータを削除したものの、繰り返し作成されるため府警サイバー犯罪対策課に相談。2018年6月14日に、男子学生に任意同行を求める形となりました。
セキュリティ管理体制の甘さが指摘される
今回の事案では、大学側の非常に甘いセキュリティが指摘されています。
そもそも学生が教員用PCを使用できた理由は、「PC端末にIDとパスワードが書かれたシールが貼られていた」から。これではIDとパスワードの意味がありません。更に附属病院では個人が特定できる患者データの持ち出しを禁止してたものの、一部の教員はUSBメモリに保存し、持ち歩いていたことも発覚。認識の甘さを浮き彫りになった形です。
今回は学生の動機が「講義データの入手」にありました。しかし、より悪意のある動機であれば被害が拡大していたことは確実です。






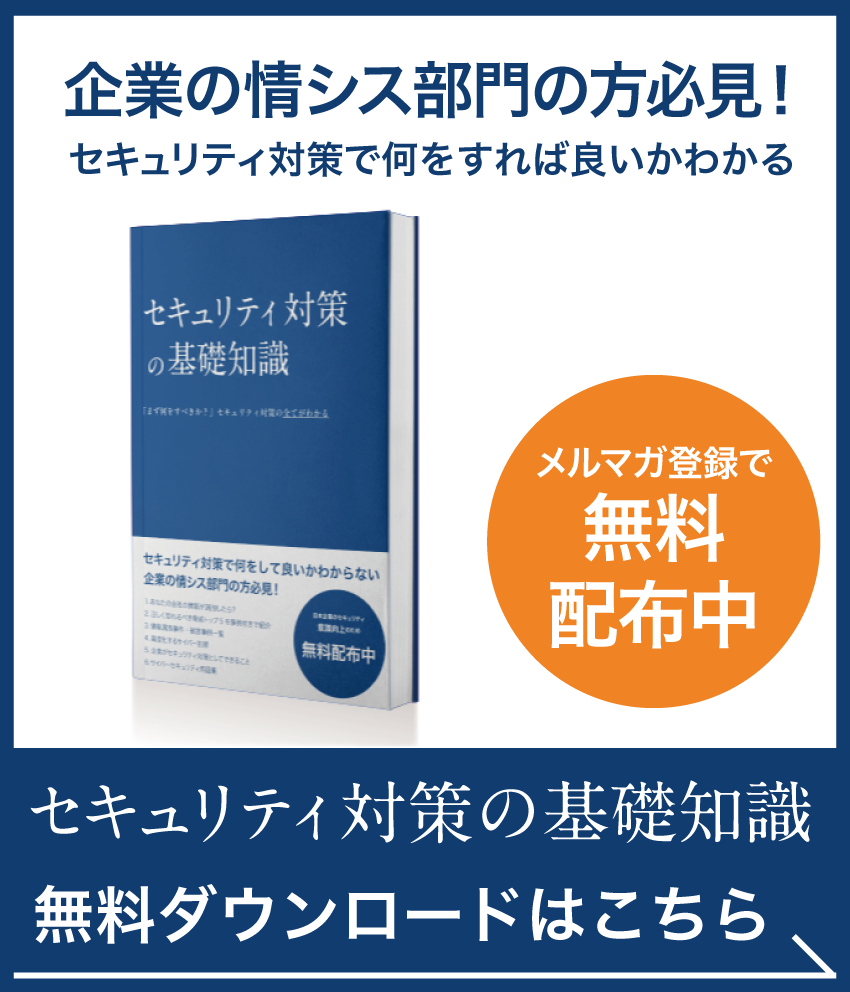
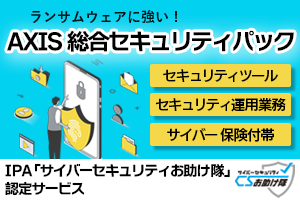
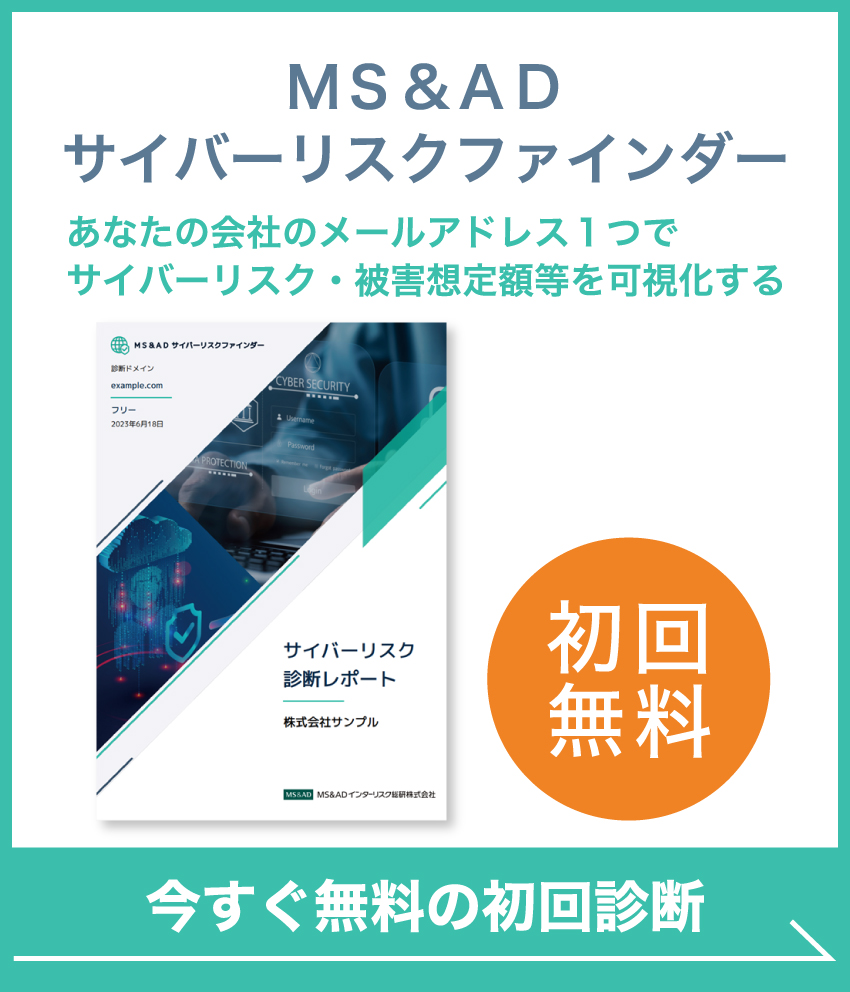















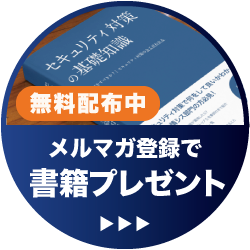
![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)


