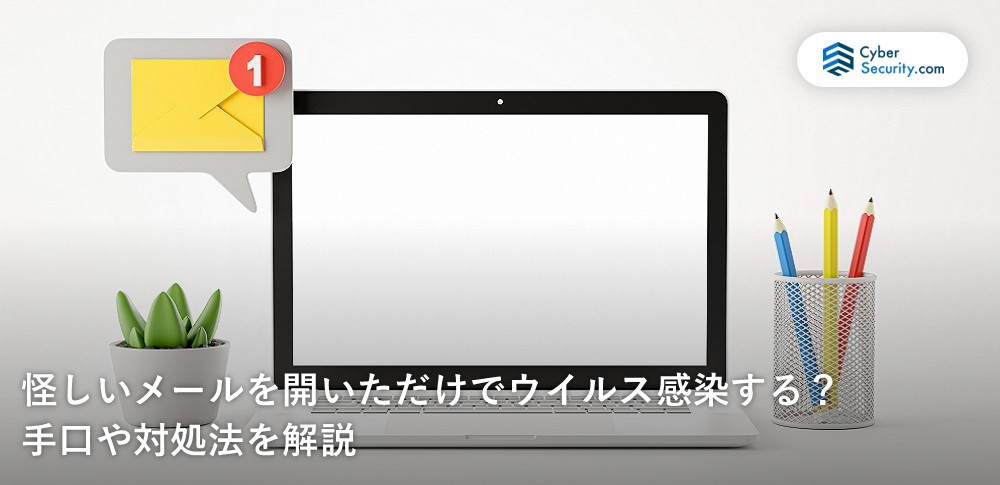
最近、不審なメールが増えて不安を感じている方も多いのではないでしょうか。「メールを開いただけでウイルス感染?」や「怪しいURLをクリックしてしまった」といった心配が尽きません。
実際メールを開いただけで感染することは稀ですが、HTMLメールや不審なリンクには注意が必要です。リンクをクリックすることでウイルス感染や個人情報漏洩のリスクが高まります。
もしウイルス感染や不正アクセスの可能性がある場合は、専門の調査会社に相談することが重要です。
この記事では、メール経由のリスクとその対処方法を解説し、専門業者への依頼方法もご紹介します。
目次
怪しいメールが引き起こすウイルス感染のリスクと影響
怪しいメールによるウイルス感染は、以下のような深刻な影響を及ぼす可能性があります。
アップデートの放置による脆弱性
OSやソフトウェアの脆弱性が発見されると、ベンダーが修正プログラムを提供しますが、バージョンを適用しないとセキュリティホールが残り、ウイルス感染のリスクが高まります。定期的にアップデートを行わないと、攻撃を受けやすくなります。
また、ベンダーが対策を施す前に脆弱性を突かれることもあるため、致命的な脆弱性が発見された場合は、ネットワークをオフラインにして外部からのアクセスを遮断することが重要です。オフラインによりマルウェア感染や遠隔操作、情報漏洩などのさらなる被害拡大を防ぐことができます。
セキュリティ対策の不足
セキュリティ対策が不十分だと、不正なメールをブロックできず、ウイルスを開封してしまう危険があります。例えば、ウイルス対策ソフトが古いままだったり、OSと互換性のないセキュリティソフトを使用していると、効果的に防御できません。
最新のウイルス対策ソフトを使用し、オペレーティングシステムやソフトウェアを常に最新の状態に保つことが、ウイルス感染を防ぐためには非常に重要です。
動作が不安定になる
ウイルスに感染すると、普段通りの使用方法でもデータ通信量が増加する場合があります。ウイルスがバックグラウンドで不必要な処理を実行し、個人情報(電話番号、住所、クレジットカード情報など)を外部に不正に送信したり、仮想通貨のマイニングを行ったりするためです。
結果、パソコンやスマートフォンの動作が遅くなったり、不安定になったりすることがあります。感染したウイルスがシステムリソースを消費し、アプリケーションが正常に動作しなくなったり、システムが頻繁にクラッシュすることがあります。
>不正アクセス・ハッキング調査の方法や端末調査ができるおすすめ調査会社を徹底解説
不正な決済が行われる
ウイルスに感染すると、個人情報やクレジットカード情報が盗まれ、金銭情報が悪用されるリスクがあります。カード情報が盗まれると、不正な決済が行われたり、オンラインショッピングで勝手に購入されることがあります。また、銀行口座の情報が盗まれ、無断で送金される可能性もあります。感染が疑われる場合は、すぐに金融機関に連絡し、取引内容の確認やカードの停止手続きを行うことが非常に重要です。
また、偽サイトから不明なソフトウェアやアプリをインストールした後、以下のような現象が発生した場合、ウイルス感染によって勝手に購入や課金が行われている可能性があります。
- 身に覚えのないアプリや有料コンテンツの請求が届く
- ECサイトで不正決済が行われている
上記状況が発生した場合は、すぐにサービス運営元に問い合わせ、アカウントを停止することが大切です。
乗っ取りによりウイルスが拡散する
ウイルスに感染すると、コンピュータやスマートフォンが不正に操作されることがあります。感染したデバイスが乗っ取られると、攻撃者はそのデバイスを利用して他の人にウイルスを拡散させることができます。
例えば、感染した端末から友人や同僚にウイルスを含んだメールを送信したり、不正なリンクをクリックさせることが考えられます。これにより、感染が広がり、さらに多くの人が被害に遭う可能性があります。
また、ウイルスに感染したスマートフォンやパソコンは、不特定多数にスパムメール(ウイルス)をばら撒くサイバー攻撃の「踏み台」として悪用されることもあります。乗っ取り状態を放置すると、情報が抜き取られるだけでなく、加害者となる恐れもあります。
もし、以下のような症状が確認できる場合は、ハッキングされている可能性があるため、速やかに対応を取ることが重要です。
- 急激な動作の遅延
- 自分では送信していないメールが送信されている
- 知らないアプリや設定の変更がされている
上記症状が発生した場合、すぐにデバイスのセキュリティを確認し、専門家に相談することをお勧めします。
個人情報漏えいの可能性がある
ウイルスに感染すると、個人情報が漏えいし、ネット上で公開されるリスクがあります。特に漏えいした情報は、ダークウェブで取引されることがあり、悪用される可能性が高まります。
個人や企業に対するターゲット型のサイバー攻撃では、嫌がらせや攻撃の一環として、漏えいした情報が「ドキシング」(晒し行為)されることもあります。これは、特定の対象を困らせたり、傷つけたり、危険にさらすことを目的に行われることがあり、被害者にとって深刻な問題となります。
個人情報漏えいを防ぐためには、ウイルス感染を未然に防ぐためのセキュリティ対策や、感染後の速やかな対応が不可欠です。
>個人情報が漏洩した?今すぐチェックできるツールやおすすめの調査会社を徹底解説
怪しいメールの主な手口
怪しいメールは、個人情報を不正に取得したり、デバイスを感染させたりする目的で送られます。
主な手口には以下の3つです。それぞれの特徴を理解して、怪しいメールに対して注意を払うことが重要です。
スパムメール
スパムメールは無差別に大量送信される迷惑メールで、主に商業目的や広告が含まれています。
送信者は信頼できない企業名や偽の情報を使い、受信者にクリックを促すことが多いです。スパムメールの手口はメールにて賞品や金銭的インセンティブを提供する内容が多く、偽のオファーや不正なリンクが含まれています。
リンクをクリックすると、個人情報を入力させる悪質なウェブサイトに誘導されることがあります。また、受信者が返信すると個人情報が収集される危険もあります。
スパムメールの特徴として、差出人が不明、信頼できない企業名、急かすような言葉を使用し、緊急感を煽る点が挙げられます。ほか、添付ファイルにウイルスが仕込まれている場合もあり、開かないように注意が必要です。
>偽サイトに個人情報を入力してしまったらどうすればよい?対処法と危険性を徹底解説
フィッシングメール
フィッシングメールは、信頼できる団体や企業を装い、偽のリンクをクリックさせることで個人情報を盗む手口です。
多くの場合、メール内には「アカウントが不正にアクセスされました」「パスワードを再設定してください」など、緊急を装った内容が含まれています。
メールに記載されたリンク先は本物のサイトに似せた偽サイトで、ユーザーが入力した情報(ID、パスワード、クレジットカード番号など)が盗まれます。金融機関やオンラインストアをターゲットにすることが多く、特に注意が必要です。
マルウェア付きメール
マルウェア付きメールは、悪意のあるソフトウェア(マルウェア)が添付されたメールで、開封するとデバイスに感染し、個人情報が盗まれる危険があります。メール内には、添付ファイルやリンクが含まれており、それらを開くことでウイルスやランサムウェア、スパイウェアなどがデバイスにインストールされます。
マルウェア感染すると、デバイスの動作を遅くしたり、個人情報を盗んだり、さらにデータを暗号化して身代金を要求することもあります。マルウェア付きメールの特徴として、差出人が不明だったり、急かすような内容が含まれていたり、添付ファイルやリンクに不審な点がある場合が多いため、慎重に扱うことが重要です。
>マルウェアに感染した?原因究明や被害調査の対応方法を徹底解説
怪しいメールの見分け方
怪しいメールを見分けるためには、以下の点に注意することが重要です。
不自然な送信元や緊急性を強調
送信元が不明だったり、信頼できないドメインから送られてきている場合は注意が必要です。
また、メールの内容に「今すぐ対応が必要」や「アカウントが危険にさらされています」など、緊急性を強調する表現が使われている場合も要注意です。正規の企業は、通常、冷静で詳細な対応方法を案内します。
不審な日本語や過度なプロモーション
メール内に不自然な日本語(誤字や意味が不明瞭な文)が含まれている場合や、過度な割引や賞品提供を示唆する内容がある場合は、スパムやフィッシングメールの可能性が高いです。特に、あまりにも魅力的なオファーが突然送られてきた場合には警戒しましょう。
不審なファイルの添付、個人情報要求
不審なメールに添付されたファイル(特に拡張子が.exeや.zipなど)の開封は避けましょう。また、パスワードやクレジットカード情報、社会保障番号などの個人情報を求めるメールも怪しいです。信頼できる企業は、メールで直接個人情報を求めることはほとんどありません。
メール本文を開いた際にウイルス感染の有無を確認する方法
メール本文を開いた際にウイルス感染を確認するには、以下の方法を活用しましょう。
セキュリティソフトで確認する
最新のセキュリティソフトやアンチウイルスソフトを使用して、受信したメールの添付ファイルやリンクをスキャンしましょう。多くのセキュリティソフトには、メール内の添付ファイルやリンクを自動的にチェックし、ウイルスやマルウェアを検出する機能があります。特に、リアルタイムスキャン機能を有効にしておくことを推奨します。これにより、ファイルを開く前にリスクを早期に検出できるため、感染のリスクを大幅に減らすことができます。
また、セキュリティソフトは定期的にアップデートし、最新のウイルス定義ファイルを保持しておくことが重要です。定期的なアップデートにより、新たに発見されたウイルスやマルウェアに迅速に対応でき、感染リスクを最小限に抑えることができるし、最新の脅威から保護される状態を維持することが可能となります。
添付ファイルとリンクの確認
不明な送信者からのメールに添付された実行可能ファイル(.exe、.zip、.bat、.jsなど)やリンクは、ウイルスやマルウェアのリスクが高いため、開かずに削除しましょう。特に、リンク先が偽サイトである場合があるため、カーソルを合わせてURLを確認し、公式サイトかどうかをチェックすることが重要です。
フィッシング攻撃では、「マクロ」を悪用することがあります。マクロはExcelなどの自動化機能で、悪用されるとウイルス拡散やファイルの不正書き換えが可能です。代表的なマクロウイルス「Emotet」は、添付ファイルを通じて感染し、セキュリティリスクを引き起こします。
>Emotet に感染した場合の対処法とは?感染経路や被害調査法を解説
怪しいメールによるウイルス感染を防ぐための対策方法
ウイルス感染を防ぐ対策方法は次のとおりです。
- 非正規ルートのアプリはインストールしない
- 届いた文面を検索して信頼性を確認する
- セキュリティ設定を見直す
- OSやアプリを最新版にアップデートする
- キャリア決済の限度額を設定する
- 専門の調査会社に調査を依頼する
非正規ルートのアプリはインストールしない
アプリケーションやソフトウェアをインストールする際は、必ず公式のアプリストア(Google PlayやApp Store)からインストールするようにしましょう。特にAndroidでは、非正規ルート(サードパーティのウェブサイトなど)からのアプリもインストール可能ですが、リスクが伴います。
不正なアプリをインストールした場合、すぐに削除し、重要なパスワードやセキュリティ設定など速やかに変更することをお勧めします。設定変更により、個人情報の漏洩やデバイスの感染を防ぐことができます。また、情報漏洩が心配な場合は、専門の調査会社に相談することをおすすめします。
届いた文面を検索して信頼性を確認する
ウイルスや詐欺目的のメッセージは、多くのユーザーに同じ内容のメッセージを大量に送信するため、ウェブで検索すると類似の詐欺報告事例にたどり着くことができます。届いたメッセージの文面をまず検索して、過去に同じような詐欺が報告されていないかを確認しましょう。
ただし、注意点として、メッセージ内のリンクをコピペして検索エンジンに入力することは避けるべきです。リンクをコピペすることで、不正なサイトに誘導され、ウイルスをダウンロードさせられるリスクがあります。リンクを直接クリックせず、ウェブサイトを公式に検索して確認するようにしましょう。
セキュリティ設定を見直す
スマートフォンの初期設定では、提供元不明の非正規ソフトやアプリはインストールできないようになっています。設定を自分で変更しない限り、問題は発生しません。しかし、設定を変更してしまうと、不正なアプリを意図せずインストールしてしまうリスクがあります。セキュリティ設定はむやみに変更せず、デフォルトのまま維持することが重要です。
また、オンライン決済やECサイトのログイン時には、IDとパスワードに加えて、二段階認証(2FA)などの本人認証を導入し、セキュリティを強化しましょう。セキュリティの強化により、不正アクセスを防ぎ、個人情報を守ることができます。
OSやアプリを最新版にアップデートする
ウイルスやマルウェアは、OSやアプリの脆弱性を利用して侵入します。古いバージョンのソフトウェアは、セキュリティの穴が開いている可能性が高いため、サイバー攻撃やハッキングのリスクが増加します。
OSやアプリを常に最新のバージョンにアップデートすることは非常に重要です。定期的にアップデートを確認し、セキュリティパッチを適用することで、リスクを最小限に抑えることができます。
キャリア決済の限度額を設定する
個人情報の流出に備えるため、キャリア決済を利用する際は慎重な対策が必要です。IDやパスワードが不正に取得されると、キャリア決済で不正な支払いが行われる可能性があるため、利用限度額を低く設定しておくことが効果的です。
また、キャリア決済が不要な場合は、機能を無効にしておくことも重要な対策です。無効対策を講じることで、万が一個人情報が流出しても、被害を最小限に抑えることができます。
専門の調査会社に調査を依頼する
ウイルス感染の有無や痕跡を個人で特定するのは困難です。かといって、スマホやPCを乗っ取られているにもかかわらず、そのまま端末の使用を続けると、ウイルスメールを周囲にばらまいてしまうなど、さらなる被害につながりかねません。
ウイルス感染の経路や被害・手口はさまざまであるため、正確な事実確認を行いたい場合は、ウイルス感染調査に対応している業者まで相談することが最善です。
また、業者によっては、最短当日での調査も対応しているため、被害防止・抑制を迅速に行うことができます。中には、相談から見積りまで無料で対応している業者もあるため、個人での対処が難しい場合は、専門業者に相談してみましょう。
ウイルス感染の調査会社を選ぶポイントや費用などは、こちらの記事でも詳しく解説しておりますので、参考にしてみてください。
おすすめのフォレンジック調査会社
公式サイトデジタルデータフォレンジック
編集部が厳選したおすすめのフォレンジック調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。
デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。
24時間365日の相談窓口があり、緊急時でも安心です。相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。
まとめ
ウイルス感染の影響を最小限に抑えるためには、不審なメールやリンク、添付ファイルを開かないことが重要です。もし感染の疑いがある場合、自身で対処するのが不安な方は、高い技術を持つ専門家に調査を依頼するのも一つの方法です。
予防のためにも、常に警戒心を持ち、不審なサイトやメールは開かずに削除するよう心がけましょう。






![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



