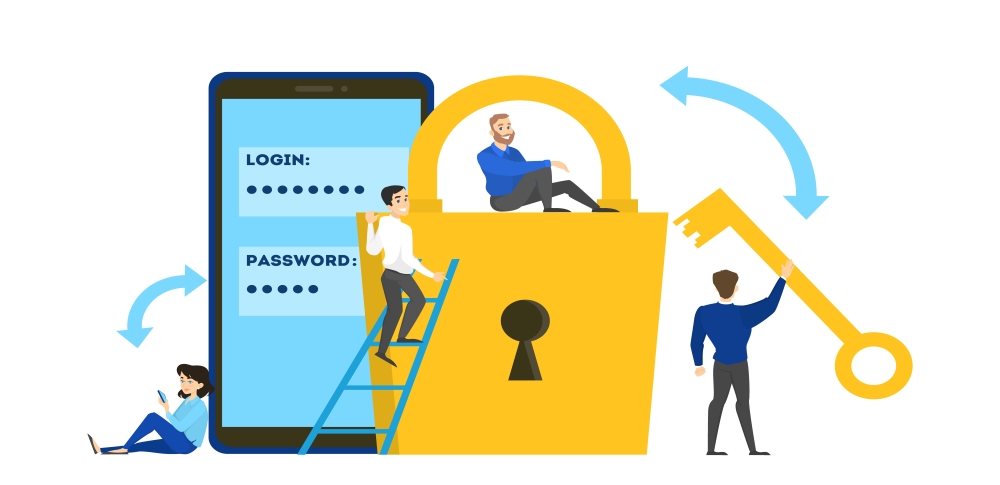
パソコンに表示された警告画面を信じて、記載されていた電話番号に連絡してしまった場合、その後どうなるかを想像したことはあるでしょうか。電話口では不安を煽る言葉で冷静な判断力を奪われ、指示に従ってしまうことで、金銭の支払いや遠隔操作などの被害に繋がる恐れがあります。
こうした警告の多くは、本物のウイルス感染ではなく「サポート詐欺」と呼ばれる詐欺行為です。しかし、途中で異変に気付き正しく対応できれば、被害を最小限に抑えることも可能です。
この記事では、偽警告につられて電話してしまった場合に起こり得ることや、具体的な対処法、被害例、再発を防ぐための予防策について解説します。
目次
パソコンの警告音と共に表示されるサポート詐欺の警告画面とは
パソコンの操作中に警告音が鳴り、「ウイルスに感染しています」「トロイの木馬ウイルスが検出されました」といった画面が表示され、そのまま記載された電話番号に連絡してしまうケースがあります。
電話をかけると、サポート担当を名乗る相手から次々と指示が出され、不安なまま操作や設定変更を行ってしまうことも少なくありません。
このような警告画面では、「050」から始まるIP電話番号や、「0120」のフリーダイヤル、「+0101」などの国際電話番号が表示されるケースが多く確認されています。しかし、画面に表示された番号であっても、正規のサポート窓口とは限らず、そのまま信用して電話をかけるのは非常に危険です。
不審に感じた場合は、すぐに発信せず、表示された番号をインターネットで検索し、詐欺に使われていないかを確認しましょう。また、「パソコン画面に表示された電話番号には連絡しない」といったルールを、あらかじめ家族内で共有しておくことも、被害防止につながります。
パソコンの警告音を信じて電話してしまった場合に起こる被害
「トロイの木馬に感染しました」などの警告画面が表示され、案内に従って電話をかけてしまうと、マイクロソフトなどの正規企業を名乗る偽のサポートセンターにつながることがあります。
電話口では不安をあおられながら操作を指示され、気付かないうちに被害が拡大してしまうケースも少なくありません。
- パソコンが遠隔操作される
- 高額な料金を不正に請求される
- 情報漏洩の可能性がある場合は早急に対応する
パソコンが遠隔操作される
サポート詐欺では、相手の指示に従って遠隔操作ソフトをインストールさせられ、パソコンを外部から操作される被害が発生します。その結果、画面の内容を監視されたり、保存されている個人情報やパスワードを盗み取られたりするおそれがあります。
また、利用者が気付かないうちに不正なプログラムを仕込まれ、遠隔操作が継続されることで、被害が長期化するケースも少なくありません。
高額な料金を不正に請求される
偽のサポートセンターでは、簡単な操作を行っただけで「サポート費用」などの名目を付け、数万円から十数万円の高額な料金を請求されるケースがあります。支払い方法として、コンビニでGoogle PlayギフトカードやAppleギフトカードを購入させ、電話口でギフトコードを伝えるよう指示されることが多く見られます。
一度コードを伝えてしまうと、「入力ミスがあった」などと理由を付けて、追加の支払いを求められる場合もあります。
また、氏名を聞き出されたり、ネットバンキングを開かせて送金操作を行わせたりする手口もあり、不正送金などの被害につながるおそれがあります。警告画面に表示された電話番号からつながった相手に対して、支払いを行うことは絶対に避けましょう。
個人情報や端末内データが外部に漏洩する
サポート詐欺では、通話中や遠隔操作中に入力した情報がそのまま盗み取られ、個人情報や端末内のデータが外部に漏えいするおそれがあります。氏名や電話番号、メールアドレスだけでなく、ID・パスワード、保存されている書類や画像などが不正に取得されるケースもあります。
これらの情報が悪用されると、アカウントの乗っ取りや二次的な詐欺被害につながる可能性があるため、注意が必要です。通話中や遠隔操作中に個人情報やパスワードを入力してしまった場合、どこまで情報が取得されたのかを利用者自身で判断することは困難です。
パソコンの警告音を信じて、電話してしまった後の対処法
サポート詐欺の警告画面に記載された電話番号へ連絡してしまった場合でも、その後の対応次第で情報漏えいや金銭被害を防げる可能性があります。
偽のサポートセンターにどのような内容を伝えたか、また端末がどのような状態かに応じて、適切な対応を行うことが重要です。
以下に、状況別の主な対処方法をご紹介します。電話の内容や端末の状態に応じて試してみましょう。
- 何も話さず通話を終了する
- 警告画面を閉じてキャッシュを削除する
- 遠隔操作ソフトをアンインストールする
- カード会社や銀行などに連絡する
- 警察や公的機関に連絡する
- 端末の情報漏えい調査やサポート詐欺調査を行う
もし端末への遠隔操作や情報漏えいの可能性がある場合は、速やかに専門のサポート詐欺調査会社へ相談することをおすすめします。
何も話さず通話を終了する
サポート詐欺の警告画面に従って電話してしまった場合、相手に何も情報を伝えないことが重要です。個人情報を伝えたり、金銭の支払いやソフトのインストールなどの指示に従ったりしないようにしましょう。
警告画面を閉じてキャッシュを削除する
次に、ブラウザに表示されている警告画面を閉じ、キャッシュを削除します。これにより、偽警告が再表示される可能性を減らすことができます。
- 「Ctrl + Shift + Esc」キーを押してタスクマネージャーを開き「タスクの終了」をクリックする
- あるいは「Alt + F4」キーを押してブラウザ画面全体を閉じる
- ブラウザの設定メニューに移動する
- ブラウザに応じて「履歴」「プライバシー」「セキュリティ」などを探してクリックする
- 「キャッシュのクリア」と削除する期間を選択してキャッシュを削除する
遠隔操作ソフトをアンインストールする
偽のサポートセンターの指示に従ってリモートソフトなどをインストールしてしまった場合は、ソフトをアンインストールしましょう。外部からの不正アクセスや画面の監視を防止できることがあります。
- 「Windows+ R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」を開く
- 「コントロールパネル」と入力してEnterキーを押し、コントロールパネルを開く
- 「プログラムのアンインストール」や「アプリと機能」をクリックする
- リストからアンインストールしたい遠隔操作ソフト(TeamViewer、AnyDeskなど)を見つけてクリックする
- 「アンインストール」ボタンをクリックし、表示される指示に従ってアンインストールを完了させる
カード会社や銀行などに連絡する
万が一、電話口でクレジットカード番号や銀行口座の情報を伝えてしまった場合は金銭被害に遭う可能性が極めて高くなります。直ちにカード会社や銀行に連絡し、不正利用や情報漏えいについて報告しましょう。必要に応じて、カードの停止や口座の凍結を依頼しておくと安心です。
警察や公的機関に連絡する
サポート詐欺の被害に遭った場合は、警察や消費生活センターなどの公的機関に連絡し、被害状況を報告することが重要です。これらの機関では、被害内容の相談受付や記録、今後取るべき行動についての助言を受けられる場合があり、被害情報が集まることで注意喚起や再発防止にも役立てられます。
また、サポート詐欺を含む情報セキュリティ上の脅威については、IPA(情報処理推進機構)でも注意喚起や被害事例が公開されています。公的機関が発信する情報を確認することで、詐欺の手口や被害傾向を把握し、今後の予防対策を検討する参考になります。
一方で、これらの公的機関は、端末の遠隔操作を停止したり、不正アクセスに対して技術的な対応を原則として行ったりすることはできません。また、相談時間や対応範囲が限られている場合もあるため、被害が進行している状況では、迅速な技術対応が難しい点には注意が必要です。
端末の情報漏えい調査やサポート詐欺調査を行う
サポート詐欺の被害に遭い、「電話の指示に従って遠隔操作ソフトをインスト―ルしてしまった」「パスワードが勝手に変更された」「頻繁に不正アクセスされる」といった被害が発生している場合、遠隔操作ソフト等を通じて遠隔操作や情報漏えいが行われた可能性があります。単に遠隔操作ソフトを削除しただけでは何の情報が漏洩したかなど知ることは困難です。
偽のサポートセンターに端末を操作された場合は、遠隔操作アプリは削除せず専門家によるサポート詐欺調査や情報漏えい調査を実施することをおすすめします。さらに心配であればネットワークを切断しましょう。
サポート詐欺調査では「フォレンジック」と呼ばれる電子端末内のデータを保全し、解析する警察の捜査でも使われる専門技術が使われます。この調査を行うことで、遠隔操作ソフトによる被害の範囲や外部に端末の情報を流出させていないかなど詳細に調査することができます。
また、サポート詐欺調査会社の中には、警察や個人情報保護委員会などの公的機関にそのまま提出できる調査報告書を作成できるところもあります。調査会社に相談する際は、目的に応じて利用しましょう。
おすすめのサポート詐欺調査会社
公式サイトデジタルデータフォレンジック
編集部が厳選したおすすめのサポート詐欺調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。
デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。
24時間365日の相談窓口があり、緊急時でも安心です。相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。
パソコンの警告音詐欺に二度と騙されないための具体的な予防策
パソコンの警告音詐欺は、事前に正しい知識と対策を知っておくことで、被害を防げる可能性が高まります。特に、「怪しいかどうかを自分で判断しようとしない仕組み」を作っておくことが重要です。
ここでは、日常的に実践でき、再発防止につながる具体的な予防策を紹介します。
- セキュリティソフトを定期的に使用する
- 遠隔操作や支払いに応じた経験は必ず記録を残す
- ブラウザの通知・ポップアップを完全にブロックする
- 電話番号での詐欺を仕組みで遮断する
セキュリティソフトを定期的に使用する
警告音やウイルス感染を示す画面が表示された場合でも、内容を自分で判断せず、まずはインストール済みのセキュリティソフトで端末をスキャンしましょう。
スキャンの結果、問題が検出されなければ、その警告は詐欺である可能性が高いと判断できます。
- セキュリティソフトを起動する
- クイックスキャン、またはフルスキャンを実行する
- 検出結果を確認し、問題がなければ画面を閉じる
「警告が出たら必ずセキュリティソフトで確認する」というルールを決めておくことで、冷静な対応につながります。
遠隔操作や支払いに応じた経験は必ず記録を残す
過去に遠隔操作や支払いを求められた経験がある場合は、どのような警告画面が表示されたのか、相手に何を言われたのかを具体的に記録しておきましょう。
画面の文言や電話番号、指示内容をメモしておくことで、次に同じ、または似た手口に遭遇した際に、詐欺だと素早く気付けるようになります。
ブラウザの通知・ポップアップを完全にブロックする
サポート詐欺の警告画面は、ブラウザの通知機能やポップアップを悪用して表示されることがあります。そのため、通知設定やポップアップ設定を見直し、不要な表示を事前に遮断しておくことが有効です。
- ブラウザの設定画面を開く
- 「プライバシー」「セキュリティ」「通知」などの項目を選択する
- 許可されている通知を確認し、不要なサイトを削除する
- ポップアップを「ブロック」に設定する
- 使っていない拡張機能や不審な拡張機能を削除する
これらを行うことで、詐欺画面が表示されるリスクを下げることができます。
電話番号での詐欺を仕組みで遮断する
サポート詐欺では、「050」や「0101」などの番号を使い、警告画面から電話をかけさせようとします。このような被害を防ぐためには、「画面に表示された電話番号には連絡しない」という行動ルールを明確にしておくことが重要です。
- 警告画面に電話番号が表示されても発信しない
- 表示された番号は必ず検索して確認する
- 家族でパソコンを共有している場合は、このルールを事前に共有する
このように仕組みとしてルール化しておくことで、焦って判断してしまう状況を防ぐことができます。
まとめ
サポート詐欺は、一度引っかかると再び狙われやすいという特徴があります。 しかし、正しい対処と予防策を実践すれば、同じ手口に騙されるリスクを大きく減らすことができます。
警告音や画面に驚いて電話してしまった方も、この記事の対処法と予防策を参考に、冷静に対応してください。
仮に電話の指示に従って遠隔操作ソフトをインストールしてしまった場合は、被害の全容を正確に把握するために、フォレンジック調査の専門家まで相談しましょう。







![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



