
顧客情報は企業にとって極めて重要な資産であり、万が一の持ち出しは信用失墜や法的リスクに直結します。とくに退職者や不満を持つ従業員による不正な情報持ち出しは、実際の業務現場で繰り返し発生しています。
こうした事態が発覚した際に、適切な対応をとるためには「証拠の確保」が不可欠です。本記事では、顧客情報の持ち出しに関する典型的な手口と、証拠の収集・調査の方法、さらに再発防止策まで解説します。
顧客情報の持ち出し手口
顧客情報の不正な持ち出しは、主に内部関係者によって行われ、巧妙かつ多様化しています。特に退職前や在宅勤務中に発生しやすく、企業の監視が行き届かないタイミングが狙われます。代表的な手口は以下の通りです。
- USBメモリや外付けHDDへの保存
- 個人のメールアドレスへの転送
- クラウドストレージへのアップロード
- スマートフォンによる画面撮影
以上の手口は、システム上に転送履歴などの痕跡が残らず、発覚しにくいのが特徴です。特に物理的な監視が難しいテレワーク環境では、このようなアナログ手法が用いられるケースが増えています。
そのため、実際に情報が持ち出されたかを確認するには、操作ログなどを適切に保全・解析できるフォレンジック調査の実施が必要です。直接的な証拠が乏しい場合でも、関連行動の痕跡を分析することで不正の有無を明らかにできます。
顧客情報の持ち出しの証拠の収集方法
持ち出された顧客情報の所在や持ち出し方法を明らかにするためには、技術的な証拠の収集が不可欠です。ここでは、具体的にどのようなデジタル証拠が重要になるのかを解説します。
- メール・チャット履歴
- アクセスログ・ファイル転送記録
- USB・外部デバイスの使用履歴
- 削除データの復元
メール・チャット履歴
従業員が社外へ情報を送信した形跡は、業務用メールやチャット履歴に残されている場合があります。特に、私用アドレスへの転送やクラウドリンクの共有履歴、特定キーワードのやり取りなどが見られた場合は、持ち出しの証拠として活用可能です。TeamsやSlackなどのログも対象となります。ログは改ざん・削除される前に速やかに保全し、調査対象者とのやりとりを時系列で追うことで、動機や関与の程度も明らかになります。
アクセスログ・ファイル転送記録
ファイルサーバやCRMシステムへのアクセス記録は、誰が・いつ・どのデータにアクセスしたかを示す重要な証拠です。また、NASや共有フォルダからの一括コピー、急激なアクセス数の増加、深夜帯の操作など、通常と異なる挙動は持ち出しの兆候とされます。加えて、社内システムから外部に送信されたファイルのログなども確認しましょう。このようなログは誤操作などで削除・上書き・改ざんされるとその後の法的措置に影響がでるため、専門家と連携することをおすすめします。
以下の記事では、操作やアクセスログの調査会社の選ぶポイントについて解説しています。今回の記事と併せて参考にしてください。
USB・外部デバイスの使用履歴
USBメモリや外付けHDD、SDカードなどの外部デバイスを業務端末に接続した履歴は、WindowsやmacOSのシステムログに記録されています。特に退職直前や深夜など、通常と異なるタイミングでの接続履歴は、不正な情報持ち出しを示す重要な兆候です。また、デバイスIDやボリュームラベルをもとに、過去に接続されたデバイスを特定することも可能です。
削除データの復元
不正行為を隠蔽するために、従業員が証拠となるファイルや履歴を削除してしまうこともあります。しかし、削除されたデータであっても、完全に消去されたとは限りません。フォレンジックツールを用いれば、削除済みのファイル、USB接続履歴、操作ログの復元が可能な場合があります。
特にPCのローカルドライブ、メールアプリの一時フォルダ、クラウドのゴミ箱などは調査対象となります。復元されたデータが決定的な証拠となることも多いため、電源の切断や書き込み操作の禁止などの初動対応が極めて重要です。
顧客情報持ち出し調査の流れ
顧客情報の持ち出しが疑われる場合、証拠の保全・調査・報告・処分という段階的なプロセスを踏むことが重要です。以下に、企業がとるべき実務的な対応フローを順に解説します。
- 顧客情報持ち出しの証拠保全を行う
- フォレンジック調査を行う
- 漏洩が発覚したら顧客と行政機関に報告する
- 内容証明郵便を送る
- 懲戒処分を行う
- 民事訴訟や刑事告訴を行う
顧客情報持ち出しの証拠保全を行う
調査を開始する前に最も重要なのは、証拠の改ざん・消去を防ぐための「保全」です。具体的には、対象となるPCやメールアカウント、ファイルサーバ、クラウドストレージなどへのアクセスを制限し、操作ログやファイルの状態をそのまま保つ必要があります。
また、デバイスの電源は入れたままにし、記録されたメモリや一時ファイルの内容を保存できる状態を保つことが推奨されます。誤った対応により証拠が失われると、加害者側に責任を問うことが難しくなるため、慎重かつ迅速な対応が求められます。
フォレンジック調査を行う
証拠保全後は、専門的なフォレンジック調査を実施し、実際に顧客情報が持ち出されたかどうかを技術的に確認します。調査では、PCやスマートフォン、サーバに残された操作ログやファイル履歴、USB接続履歴、削除データなどを復元・分析します。調査によって、誰が・いつ・どのように・何の情報を持ち出したのかを明確化することが可能です。
また、専門家に調査を依頼した場合、調査結果は報告書としてまとめられ、懲戒処分や訴訟の証拠として活用されることもあります。自社対応が難しい場合は、外部のフォレンジック調査会社への依頼が現実的かつ確実です。
漏洩が発覚したら顧客と行政機関に報告する
フォレンジック調査等によって顧客情報の漏洩が確認された場合は、関係者への報告が必要です。とくに個人情報が含まれる場合は、本人(顧客)への通知と、個人情報保護委員会への報告が義務付けられるケースがあります。
報告の際は、漏洩した情報の範囲、原因、再発防止策を明確にし、誠実に対応することで企業の信頼失墜を最小限にとどめることができます。報告が遅れたり不十分だったりすると、行政指導や損害賠償請求のリスクが高まるため、法令に則った対応が不可欠です。
内容証明郵便を送る
持ち出し行為が判明した従業員や元社員に対しては、まず法的な意思表示として「内容証明郵便」を送付することが有効です。内容証明は、送付内容・日付・相手が受け取った事実が公的に記録されるため、後の訴訟や示談交渉での証拠として役立ちます。
内容には、持ち出し行為の詳細、損害の発生、即時の情報返還や削除の要求、再発防止を求める旨等を明記します。弁護士を通じて作成することで、より法的な重みと説得力を持たせることができます。
懲戒処分を行う
社内規定に違反して顧客情報を持ち出した従業員に対しては、就業規則に基づいた懲戒処分を行う必要があります。処分の種類には、戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇などがありますが、事実関係や被害の重大性に応じて適切な対応を判断します。
懲戒処分を行う際には、調査結果や証拠をもとに、社内規程に従って手続きを踏むことが重要です。処分の妥当性が問われる場面も想定されるため、記録と理由付けを明確に残しておくべきです。
民事訴訟や刑事告訴を行う
持ち出された顧客情報が重大な被害を引き起こした場合、企業は民事訴訟によって損害賠償を請求することが可能です。また、不正競争防止法違反や個人情報保護法違反、窃盗罪などに該当する場合は、警察への刑事告訴も選択肢となります。
訴訟や告訴には、事前に顧客情報が持ち出されたという確かな証拠が求められるため、フォレンジック調査を含めた念入りな証拠収集及び、弁護士と連携しながら対応を進めることが望まれます。
フォレンジック調査ができるおすすめ調査会社
顧客情報持ち出しの事実を電子端末のログやデータから明らかにするフォレンジック調査は、まだまだ一般に馴染みが薄く、フォレンジック調査会社選びの際もどのような判断基準で選定すればよいか分からない方も多いと思います。
そこで、対応領域や費用・実績などを踏まえ、50社以上の中から見つけたおすすめのフォレンジック調査会社・調査会社を紹介します。
デジタルデータフォレンジック
デジタルデータフォレンジックは、国内売上No.1のデータ復旧業者が提供しているフォレンジックサービスです。累計3.2万件以上の相談実績を持ち、サイバー攻撃被害や社内不正の調査経験が豊富な調査会社です。
調査・解析専門のエンジニアとは別に、相談窓口としてフォレンジック調査専門アドバイザーが在籍しています。
多種多様な業種の調査実績があり、年中無休でスピーディーに対応してもらえるため、初めて調査を依頼する場合でも安心して相談することができます。
また、警視庁からの捜査依頼実績やメディアでの紹介実績も多数あることから実績面でも信頼がおけます。法人/個人問わず対応しており、見積まで無料のため費用面も安心です。法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで、幅広い対応を可能としている汎用性の高い調査会社です。
| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |
|---|---|
| 調査対象 | PC、スマートフォン、サーバ、外付けHDD、USBメモリ、SDカード、タブレット など |
| サービス | 社内不正調査、情報持出し調査、横領着服調査、パスワード解除、ハッキング・不正アクセス調査、データ改ざん調査、データ復元、マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃被害調査、退職者調査、労働問題調査、デジタル遺品、離婚問題・浮気調査 など |
| 特長 | ✔官公庁法人・捜査機関への協力を含む、累計39,451件の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスを保有する企業が調査(※)(※)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |
顧客情報持ち出しを防ぐための社内対策
顧客情報の不正な持ち出しは、発生してから対応するのではなく、未然に防ぐための仕組みづくりが重要です。ここでは、企業が実践すべき内部統制とセキュリティ体制の具体的な対策を紹介します。
- 情報持ち出し規則の策定
- ログ管理や監視を行う
- 入退社時に機密保持誓約書に記入してもらう
情報持ち出し規則の策定
まず最も基本となるのが、「顧客情報の取り扱い」に関する社内規則の整備です。どのような情報が機密情報に該当するのか、どのような行為が「持ち出し」とみなされるのかを具体的に定め、全従業員に周知する必要があります。
私用メールへの転送やUSBへの保存、私物端末での閲覧禁止などの禁止事項も明文化しましょう。また、違反時の処分規定を明記することで、抑止効果を高めることができます。定期的な見直しと研修を通じて、ルールが形骸化しないよう徹底することが大切です。
ログ管理や監視を行う
技術的な対策として有効なのが、システムや端末の操作ログ、ファイルアクセスログ、外部送信履歴などの「ログ管理」です。ログを取得・監視することで、不審なアクセスや大量のデータ転送、夜間の異常操作など、内部不正の兆候を早期に察知できます。
また、EDRやSIEMなどのセキュリティツールを活用すれば、リアルタイムでアラートを受け取ることも可能です。取得したログは、事後調査や法的対応においても有効な証拠となるため、改ざん防止と長期保管の仕組みも整備しておくべきです。
入退社時に機密保持誓約書に記入してもらう
従業員の入社・退職時には、「機密保持誓約書」の取り交わしを必須とすることが、将来的なトラブル予防に役立ちます。誓約書には、顧客情報を含む業務上知り得た機密情報を、在職中および退職後も第三者に漏らさないことを明記します。
また、情報の返却義務や、不正使用時の責任範囲、損害賠償義務なども併せて記載しておくと法的効力が高まります。書面による明確な同意があることで、退職後に情報が流出した際も、訴訟や損害請求における立証がスムーズになります。
まとめ
顧客情報の持ち出しは、企業の信頼と業績を揺るがす重大なインシデントです。発覚後の対応には冷静な初動、法的証拠の確保、専門的なフォレンジック調査が不可欠です。
情報漏洩の兆候に気づいたら、証拠を守るために速やかに保全作業を行い、必要に応じて専門調査会社へ相談しましょう。


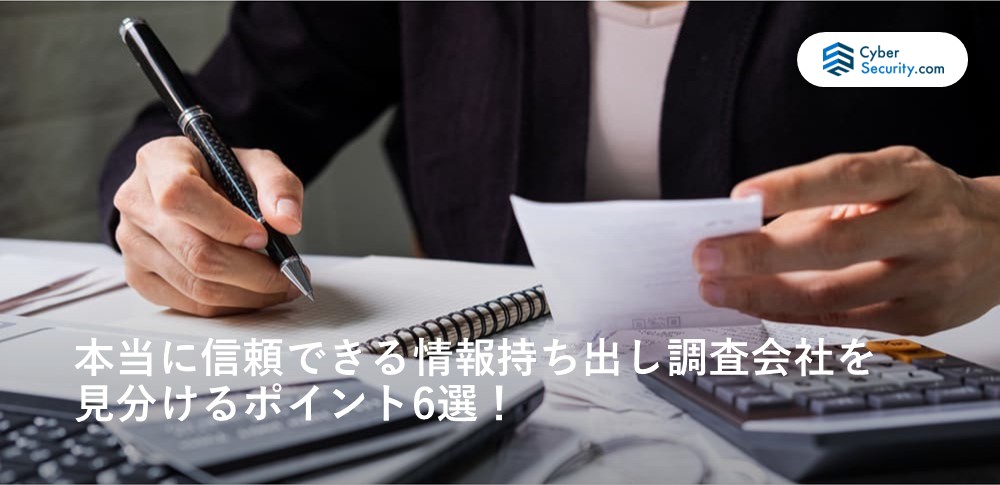








![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



