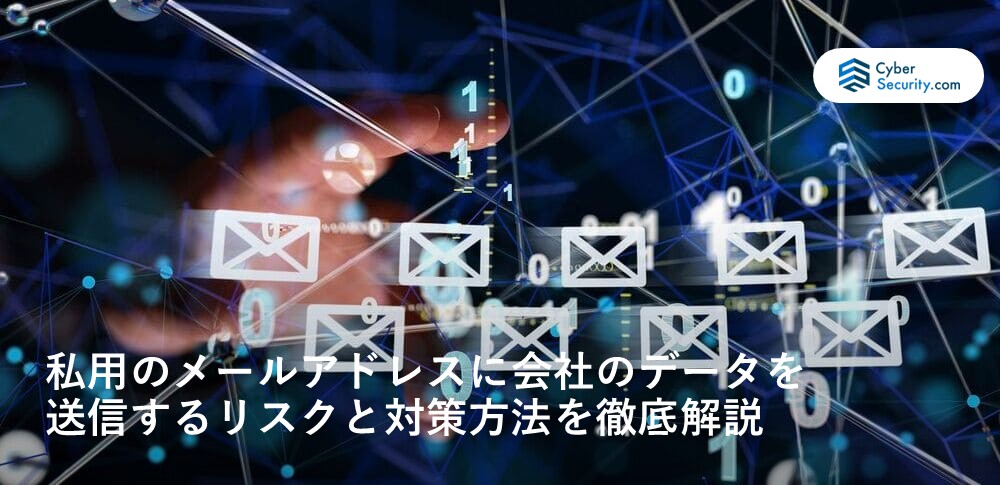
企業の機密情報や顧客データが、意図せずメールを通じて外部に流出するケースが後を絶ちません。特に近年はテレワークや私用端末の利用拡大により、メール経由のデータ持ち出しリスクが高まっています。
本記事では私用のメールアドレスに会社のデータを送信するリスク、発覚時の対処法、そして予防策までを網羅的に解説します。社内不正や内部犯行の可能性を見逃さず、万が一の備えを整えるための実践的な対策を紹介します。
既に社内で情報持ち出しが発覚し、すぐに相談が必要な場合は、以下のリンクに24時間相談可能なおすすめの調査会社を掲載しています。
目次
会社のデータがメールで持ち出される情報漏洩リスク
会社のデータがメールで持ち出される情報漏洩リスクは以下の通りです。
- 誤送信による情報漏洩
- 通信の盗聴による機密情報の漏洩
- 社外からの不正アクセスによる情報持ち出しリスク
- 従業員や退職者による意図的なデータ持ち出し
誤送信による情報漏洩
メールの宛先ミスや誤った添付ファイルの送信は、最も多い情報漏洩原因のひとつです。とくに顧客情報や契約書、設計図面などの機密文書を誤って第三者に送付してしまうと、漏洩後の回収は困難です。外部に渡った情報は拡散や再利用されるリスクがあり、企業の信用失墜や損害賠償にも発展しかねません。ヒューマンエラーであっても、企業としての責任を問われることになります。
通信の盗聴による機密情報の漏洩
外出先や自宅で公衆Wi-Fiを利用してメールを送信した場合、暗号化されていない通信内容が第三者に盗聴される恐れがあります。いわゆる「中間者攻撃(MITM)」により、送信中のメールや添付ファイルが盗まれ、機密情報が漏洩する可能性があります。メールサーバやクラウドサービスの通信経路が安全であるかどうかは、企業全体でチェックしておきましょう。
社外からの不正アクセスによる情報持ち出しリスク
外部の攻撃者が社員のメールアカウントに不正ログインし、情報を盗み取る事件も増えています。IDやパスワードが漏れた場合、攻撃者は正規の手続きを装って機密データを外部へ送信できます。このような事態では、アクセスログや送信履歴を辿ることで不正を突き止める必要がありますが、発覚が遅れれば大規模な被害に発展する恐れがあります。
従業員や退職者による意図的なデータ持ち出し
社内の人間が意図的に会社のデータを私用メールに送信し、外部へ持ち出すケースも深刻です。とくに退職間近の従業員が、顧客リストや技術資料を持ち出して競合他社へ転職する事例もあります。内部犯行は発覚しにくく、メール転送や削除で証拠を隠滅されることもあるため、後から発見しても時すでに遅しという場合があります。
会社のデータを私用のメールアドレスに送信することの法的リスク
従業員や退職者が会社のデータを私用のメールアドレスに送信することは違法です。以下のような法的リスクが発生します。
- 情報漏洩
- 不正競争防止法違反
- 懲戒解雇
情報漏洩
会社のデータを私用メールアドレスに転送する行為は、送信者に悪意がなかったとしても、情報漏洩行為と見なされるリスクがあります。とくに、顧客名簿や社員情報などの「個人情報」を含むデータであれば、個人情報保護法(令和4年改正法)第20条に基づき、適切な安全管理措置が講じられていなかったとされる可能性があります。
仮にこの行為によって情報が外部に流出した場合、企業は監督官庁(個人情報保護委員会)への報告義務を負い、違反が悪質であれば最大で1億円の行政罰が課されることもあります。本人に対しても損害賠償請求が起こることがあり、善意での送信であっても処分を免れない場合があります。
不正競争防止法違反
営業秘密(例:顧客リスト、価格表、技術仕様など)を許可なく私用メールに送信し、社外に持ち出す行為は、不正競争防止法第21条に規定される「営業秘密の不正取得・開示・使用」に該当する可能性があります。とくに退職間際の従業員や、転職先の競合企業に持ち込まれた場合は、企業側が刑事告訴または民事訴訟を提起するケースが多く見られます。
2022年改正後、刑事罰としては10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金(法人は最大5億円の罰金)が科される可能性があります。送信者だけでなく、受け取った側(転職先企業など)も共犯として処罰対象になることもあり、きわめて重大な法的リスクを伴います。
懲戒解雇
就業規則で明確に禁止されているにもかかわらず、会社の業務データを私用メールへ送信した場合、懲戒処分の対象になります。とくに「秘密情報の漏洩」や「企業秩序の著しい乱れ」として評価されると、懲戒解雇(労働契約の即時解除)に該当する可能性があります。
懲戒解雇は、退職金の不支給や失業保険の制限にも影響し、本人の社会的信用も大きく損なわれます。したがって、会社側が懲戒解雇を行うハードルは非常に高いものとなっています。メールによる情報持ち出しを理由として懲戒解雇を行うには、持ち出しの証拠が不可欠です。フォレンジック調査会社に相談すると、証拠の保全が難しいメールデータを保全・解析し、調査結果を報告書として公的機関にそのまま提出できる形にすることも可能です。
会社のデータがメールで持ち出された場合の対処法
会社のデータがメールで持ち出しされた場合の対処法は以下の通りです。
- メールアカウントの凍結・アクセス遮断
- 証拠保全する
- フォレンジック調査を行う
メールアカウントの凍結・アクセス遮断
メールによる不正なデータ持ち出しが疑われる場合、まず最初に実施すべきは「関係アカウントの緊急停止」です。対象者のメールアカウントや、関連するクラウドストレージへのアクセスを一時的に遮断し、これ以上の情報送信を防ぎます。
同時に、社内ネットワークからの接続履歴やログイン元IPを確認し、不正アクセスの可能性があるかを初期的にチェックします。システム部門・情報管理責任者・上層部を含めた緊急対策チームを編成し、証拠改ざんの恐れがある場合はすぐに端末保全にも着手しましょう。
証拠保全する
後の調査や法的対応に備えて、関係する証拠を確実に保全することは最も重要なステップです。とくにメールは削除や上書きが容易であり、保全のタイミングを逃すと、後から証拠不十分と判断されるリスクがあります。以下に保全すべき項目を整理します。
- 送信メールの原文
- 送信日時・送信元IPアドレス・デバイス情報
- 宛先アドレス
- 下書き・送信履歴・自動転送設定の有無
- メールサーバ・SMTPログ
- PC・スマホなど端末の操作ログ
- クラウド連携履歴
これらの情報は、フォレンジック調査や訴訟時の証拠にもなり得るため、可能な限り未加工・未改変の状態で保全することが求められます。操作を誤ると証拠能力が損なわれるため、フォレンジック調査会社への依頼も検討しましょう。
フォレンジック調査を行う
証拠保全後は、専門的な解析によって実際に何が行われたのかを明らかにする必要があります。そこで有効なのが「フォレンジック調査」です。対象となるPCやスマホのディスクイメージを作成し、削除されたメールや隠蔽された転送設定、ログ改ざんの有無まで詳細に解析します。
また、メール送信の動機や経路を明確化することで、内部不正なのか、外部からの侵入なのかを切り分けられます。特に裁判や損害賠償請求を視野に入れる場合、調査の信頼性が問われるため、証拠保全から報告書作成まで一貫対応できるフォレンジック調査会社の活用が推奨されます。被害を最小限に抑えるには、発覚後24時間以内に調査の方向性を決定することが理想です。
おすすめのフォレンジック調査会社
フォレンジック調査はまだまだ一般的に馴染みが薄く、どのような判断基準で依頼先を選定すればよいか分からない方も多いと思います。そこで、30社以上の会社から以下のポイントで厳選した編集部おすすめの調査会社を紹介します。
信頼できるフォレンジック調査会社を選ぶポイント
- 官公庁・捜査機関・大手法人の依頼実績がある
- 緊急時のスピード対応が可能
- セキュリティ体制が整っている
- 法的証拠となる調査報告書を発行できる
- データ復旧作業に対応している
- 費用形態が明確である
上記のポイントから厳選したおすすめのフォレンジック調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。
デジタルデータフォレンジック
公式サイトデジタルデータフォレンジック
デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。
一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。
運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。
相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。
| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |
|---|---|
| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |
| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |
| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |
| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |
| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |
会社のデータがメールで持ち出されることの予防策
会社のデータがメールで持ち出されることを予防するには、以下の方法が有効とされます。
- 機密情報にアクセス制限をかける
- メールの監視ソフトを導入する
- ログ管理ツールを導入する
- 従業員教育を行う
- 就業規則を整備する
機密情報にアクセス制限をかける
社内に蓄積されたデータの中でも、顧客リスト、営業戦略、設計図面などの機密情報は、特定の担当者のみがアクセスできる状態に制限する必要があります。アクセス制御は、役職や部署ごとに閲覧・編集権限を細かく設定します。
ファイルサーバーやクラウドストレージでは、閲覧権限・ダウンロード可否・共有リンクの制御を徹底することで、情報の不正閲覧や持ち出しリスクを抑えることが可能です。また、退職予定者や休職者の権限は速やかに削除・変更し、アクセスログの確認も怠らないようにしましょう。
メールの監視ソフトを導入する
社外宛のメールに対して、一定の条件に合致した送信を検知・記録するメール監視ツールの導入は、情報漏洩の早期発見と抑止に有効です。たとえば、送信先がフリーメールアドレス(Gmail・Yahooなど)である場合や、「顧客」「設計」「秘密」などの特定キーワードを含む本文・添付ファイルが検出された場合に、管理者へ自動通知を行う設定が可能です。
一部のツールでは、添付ファイルの強制パスワード化や、承認制ワークフローを取り入れることもでき、ヒューマンエラーや内部不正を未然に防ぎます。
ログ管理ツールを導入する
メール送信、ファイルの閲覧・編集・削除、USB接続、外部アクセスなどの操作履歴を記録・可視化するログ管理ツールは、インシデント対応において非常に重要です。何時、誰が、どの端末で、どのデータにアクセスし、どの宛先に送信したかを詳細に追跡できるため、不正行為の証拠を迅速に特定できます。
さらに、一定期間ログを保存しておくことで、発覚が遅れたケースにも対応可能です。メールに特化したログ監視機能を備えたツールを導入すれば、業務中のやり取りを自動で監査対象とし、不審な挙動をリアルタイムで検知することも可能です。
従業員教育を行う
情報セキュリティに関するルールやリスクをどれだけ整備しても、最終的に運用するのは従業員一人ひとりです。誤送信や軽率なファイル共有などの多くは、教育不足や認識の甘さに起因しています。定期的な研修では、単なる注意喚起にとどまらず、具体的な情報漏洩事例やペナルティ、想定被害額まで示すことで危機感を与えることが大切です。
また、研修内容はIT部門任せにせず、法務や人事と連携して社内全体の統一ルールとして徹底させる必要があります。新人研修や異動時、退職時にも情報管理教育を組み込むことで、継続的なリスク低減が可能になります。
就業規則を整備する
社内のセキュリティ体制を実効性あるものにするには、就業規則などの公式文書に「情報持ち出しの禁止」「私用メールへのデータ送信の禁止」「懲戒処分の基準」などを明記しておくことが不可欠です。こうしたルールがあいまいだと、違反行為が発生しても適切な処分が難しく、再発の抑止力も弱まります。また、従業員に就業規則への同意書を提出させておくことで、法的措置を講じる際の根拠としても活用できます。
まとめ
メールによる情報の持ち出しは、手軽であるがゆえに深刻なリスクを伴います。ヒューマンエラー、外部攻撃、内部不正などどの角度からも脅威は存在し、企業の信用や存続を脅かしかねません。万が一の際には証拠保全と迅速な調査が不可欠であり、事前に体制を整えておくことが重要です。
情報が持ち出された疑いがある場合は、フォレンジック調査会社に相談し、業務用パソコンやスマートフォンに残された痕跡を調査してもらいましょう。



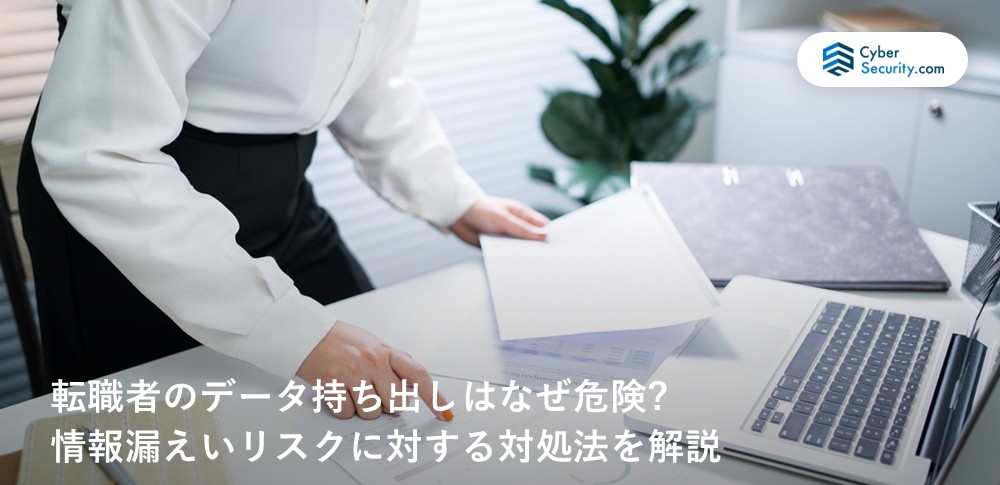





![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



