
退職者による情報・データの持ち出しは、企業にとって重大なリスクです。顧客情報や営業秘密が外部に流出すれば、取引停止・訴訟・信用の失墜といった深刻な影響を招きかねません。しかも、問題は「悪意のある不正」だけではありません。業務データの私的利用や認識不足による持ち出しでも、法的責任や賠償の対象になり得るのです。
この記事では、退職者による情報持ち出しの実態、違法となる境界線、持ち出しの典型手口、発覚時の企業対応、そして再発を防ぐための社内体制構築までを体系的に解説します。さらに、証拠調査の手段として有効なフォレンジック調査の活用法についても詳しく紹介します。
もし「退職者が情報を持ち出したかもしれない」と感じたら、初動対応の遅れが命取りです。この記事を参考に、取るべき対応を早急に検討してください。
目次
退職者による情報持ち出しが起きる背景と企業リスク
退職者による情報持ち出しは、特定の悪意ある社員だけが起こす例外的な問題ではありません。
実際には、転職や評価への不安、認識不足など、誰にでも起こり得る要因が重なって発生します。まずは、なぜ退職時に情報持ち出しが起こるのか、その背景から整理していきます。
なぜ退職時に情報持ち出しが起こるのか?
退職者による情報持ち出しは、一部の悪意ある人間だけが行う特殊な行為ではありません。
表向き勤務態度に問題ないと感じるような人でも、動機次第で簡単に境界線を越えることがあります。
企業側がこの現実を正しく認識できていない場合、「見逃されたリスク」が重大な損失につながるのです。
退職時の情報持ち出しには、主に以下の4つの動機パターンがあります。
① 転職時に自分の実績として使うため
もっともよくあるのが、転職先で即戦力として評価されたいという欲求です。
「この顧客は自分が担当していた」「この資料は自分が作った」と示すために、営業資料・提案書・顧客名簿などを「成果物」として、持ち出してしまうパターンです。
本人に悪意がない場合でも、これらの情報は通常、会社の営業秘密や社内機密として管理されており、無断での持ち出しは法的リスクを伴います。
実際の違法性の有無については、情報の性質・管理状況・持ち出し手段などに応じて判断されますが、企業としては、そうした情報の持ち出しが行われたかどうかを客観的に把握しておく必要があります。
②金銭的な利益を得るため
退職前後に、起業準備や副業、転職先での業務に備える目的で、社内情報を私的に保存するケースも見られます。
中には、価格戦略、設計資料、取引先リストなど、事業活動において価値を持つ情報が対象となることもあります。
これらの情報は、社内でどのように管理されていたか、どのような経緯で外部に持ち出されたかによって、企業への影響や法的評価が大きく異なります。
そのため企業としては、意図や目的を推測する前に、実際にどの情報が、どの手段で持ち出されたのかを客観的に把握することが重要です。
③会社に仕返しするため
人間関係のトラブルや評価への不満から、「会社に損害を与えたい」という復讐的な動機も存在します。
この場合、持ち出しだけでなく削除・改ざん・証拠隠滅など、より悪質で破壊的な行為に及ぶリスクがあります。
④誤操作や従業員の認識不足
見逃されがちですが、「悪意のない漏洩」が最も厄介です。
「私物のPCやクラウドにデータを残したまま退職してしまう」、「退職後もアクセスできる状態が放置されていた」など、本人に情報持ち出しの意識がなくても、結果として情報漏洩が発生すれば、企業には同じ損害が降りかかります。
退職者の情報持ち出しによって発生する企業リスクとは?
退職者が企業情報を持ち出した場合、その影響は一時的な情報漏洩にとどまらず、経営・法務・信用・競争力といった企業の根幹に深刻なダメージを及ぼします。
以下に、特に重要な5つのリスクとその背景を解説します。
退職者が持ち出したデータの種類にもよりますが、持ち出しが発生している場合は、フォレンジック調査による端末調査が有効です。調査会社を一覧にしてまとめた記事があるので、こちらも参考にしてみてください。
法的責任と賠償リスクが発生する
顧客情報や営業秘密の漏洩は、不正競争防止法・個人情報保護法違反として訴訟や制裁の対象となる可能性があります。
その結果、多額の損害賠償請求や行政処分、そして社会的信用の毀損といった被害が連鎖的に発生します。
東京商工リサーチの調査では、2024年の情報漏えい・紛失を公表した人数別では、1万人以上は合計51件で、うち10万人以上100万人未満は23件、100万人以上の漏洩は2件と発表しています。中でも「不正持ち出し・盗難」による漏洩は、大手保険代理店のインシデントにより、漏洩・紛失人数の平均は「22万4,782人」と大幅に引き上げられています。
このような事件は企業の調査対応や謝罪対応に膨大なリソースを要することになります。特に、顧客情報や営業秘密が持ち出された場合、企業は多額の賠償義務といった法的責任だけでなく、企業の評判や信用が低下し、経営に支障が出る可能性があります。
出典:東京商工リサーチ
競合他社に営業秘密や技術情報が流出する
退職者が顧客リストや技術資料、設計図、ソースコードなどを持ち出し、転職先や起業に活用するケースは少なくありません。
これにより、競合他社に自社のノウハウが流出し、模倣・逆利用されることで市場シェアを失う危険性があります。
特にBtoB企業では、顧客引き抜きによる契約終了や、価格競争力の喪失が短期的に発生する可能性もあります。
社内不正の証拠が隠滅される
情報持ち出しには、過去の不正を隠す目的でログやファイルを削除・改ざんするケースも含まれます。
たとえば以下のような罪に関わる証拠が消失することで、企業が適切な処分・訴訟を行えなくなるリスクがあります。
- 電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)…コンピュータを使って不正に財産的利益を得た場合に適用される犯罪です。業務システムを改ざんし、売上やポイントを操作するなどの行為が含まれます。
- 背任罪(刑法第247条)…自己や第三者の利益のために、会社に損害を与えるような業務処理を行った場合に成立します。たとえば、社内の立場を悪用して不正な契約や支払いを行う行為などが該当します。
- 横領罪(刑法第252条)…会社から預かった金銭や物品を無断で取得・使用する行為に適用されます。備品の私物化やデジタル資産の不正転用などがこれに当たります。
これらは、従業員が在職中に行った業務上の不正を裁くうえで極めて重要な証拠となるため、情報持ち出しは時に不正の真相究明の妨げになり得る点に注意が必要です。
情報管理体制の不備が信用を失墜させる
情報の漏洩・持ち出しが起きたという事実以上に、「そのようなことが起きる社内体制だった」ことが問題視されます。
顧客・取引先・株主からは、「情報管理が甘い企業」という評価がつき、契約破棄・信頼低下に直結する可能性もあります。
特に、会社の中核情報(技術、マニュアル、企画書等)が流出した場合、外部からは「再発可能性がある」と判断され、レピュテーションが急激に悪化することもあります。
不正アクセスによる二次被害を受ける
退職者が在職中に得たアカウントや権限を悪用し、退職後も社内システムに侵入するケースも考えられます。
退職前にVPNやクラウドアカウントを無効化することをしていないと、社内ネットワークへの侵入・情報の改ざんや削除が発生し、被害は拡大・長期化します。
さらに、内部犯行のため発覚が遅れがちで、気づいた時には重大なデータ損失や再漏洩が発生していることもありえます。
このような二次被害に備えるには、退職時点でのアカウント無効化・ログ調査・端末保全といった対応が必須です。
退職者による情報持ち出しの事例
過去の代表的な退職者による大規模な情報持ち出しの事例として下記のものがあります。
ソフトバンクの事例
2021年1月、ソフトバンクの元社員が5Gに関する機密情報を流出させた事件が明らかになりました。元社員は2019年11月~12月の間に、在職中にサーバーから入手したデータをクラウドストレージにアップロードし、私用メールアドレスに送信して持ち出しました。
その後、元社員は楽天モバイルに転職し、持ち出した情報を漏洩しました。ソフトバンクは2021年5月に元社員を刑事告訴し、元社員と楽天モバイルに対して民事訴訟を提起しました。2022年12月、東京地裁は元社員に対して懲役2年(執行猶予4年)、罰金100万円の判決を下しています。
出典:ソフトバンク
NTTビジネスソリューションズの事例
NTT西日本の子会社のNTTビジネスソリューションズから約900万件の顧客情報が流出した事件で、顧客情報管理システムの保守業務を担当していた元派遣社員の男が不正競争防止法違反で懲役3年、執行猶予4年、罰金100万円の判決が言い渡されています。男は、2023年1月に顧客情報管理システムの保守業務を担当していた際、約3万人分の顧客情報をコピーして名簿業者に売却しました。
さらに、情報持ち出しは2013年から2023年にかけても行われ、69の企業や自治体が管理する928万件の個人情報の流出と、約2,400万円の利益を得ていたことも捜査関係者らの調査により明らかになりました。
出典:読売新聞
違法となる退職時の情報持ち出しの境界線とは?
退職時の情報持ち出しは、すべてが直ちに違法となるわけではありません。
しかし、持ち出した情報の内容や目的、管理状況によっては、民事・刑事の責任が問われる可能性があります。
まずは、どのようなケースが法的に問題となるのかを整理しておくことが重要です。
民事/刑事で退職者の情報持ち出しが問題になるケース
退職者による情報持ち出しは、その内容や目的によって民事・刑事の両面で問題となる可能性があります。
たとえば、以下のような状況では違法性が問われることが多くなります。
- 顧客情報や営業資料を無断で私用PCに保存し、そのまま退職
- 転職先や自身の起業において、元の会社の営業秘密や顧客データなどを無断で利用するケース
- 社内での評価や人間関係への不満から、意図的に情報を持ち出す
このような事実が発覚いた場合、法人として重要なのは「退職者に情報を持ち出された事実を立証できるかどうか」です。
違法性が明らかでも、データが既に削除・改ざんされていたり、証拠が残っていなければ、企業側の法的主張は通りません。
このように、退職者の情報持ち出しは、目的や内容によって民事責任や刑事罰の対象になり得る重大な問題です。
実際に、どのような法律に基づいて違法とされるのかを理解することで、企業としての判断軸が明確になります。
次に、情報持ち出しに関わる代表的な法律である「不正競争防止法」と「個人情報保護法」のポイントを整理します。
不正競争防止法・個人情報保護法のポイント整理
情報持ち出しが法的に問題になるかどうかは、主に以下の2つの法律が関係します。
- 不正競争防止法:営業秘密の不正取得・使用・開示が該当
- 個人情報保護法:顧客情報や従業員情報の漏洩が該当
しかし、これらの法律が適用されるには、企業側が「その情報が営業秘密・個人情報として管理されていたこと」を立証しなければなりません。
つまり、「誰が」「いつ」「どの端末で」「どのデータを」「どの手段で持ち出したのか」、技術的な痕跡(ログ、操作履歴、データ残存情報など)を正確に調査・可視化できるかどうかが、企業側の明暗を分けます。
「営業秘密」の定義と認定される条件
企業が「この情報は営業秘密だ」と主張しても、裁判で認められるには3つの法的条件を満たす必要があります。
- 秘密管理性:パスワード、アクセス制限、契約書などで適切に管理されていること
- 非公知性:社外に出回っていない情報であること
- 有用性:事業活動にとって価値ある情報であること
これら3要件を客観的に満たしていたことを、企業側が証明しなければならないという点が重要です。
つまり、「この情報は大事だった」という主張だけでは不十分で、その情報が実際に管理され、秘密として扱われていた証拠が求められます。
そのため、企業が違法性を主張する前にまず行うべきなのが、事実関係の可視化と証拠の保全です。ここで重要な役割を果たすのが、フォレンジック調査になります。
専門的な技術を用いることで、操作履歴やデータの持ち出し痕跡を精密に解析し、証拠として有効な形式で保全することが可能になります。
退職者によるデータ持ち出しの主な手口
退職者がデータを持ち出す手口は多岐にわたります。物理的な持ち出しから、デジタル技術を駆使した方法まで、その種類と特徴を理解することが重要です。以下では、具体的な手段を解説します。
USBメモリなどの外部記憶装置の利用
退職者が私物のUSBメモリやポータブルHDDを使用して、業務用PCや社内サーバーからデータをコピーするケースです。顧客情報や技術情報が狙われることがあります。
- 外部記憶装置は持ち運びが簡単で、検出が難しい。
- 会社のシステムが外部デバイス接続を制限していない場合、容易に行われる。
個人メールへの送信
会社のメールアカウントを利用して、個人のGmailやYahooメールなどに機密情報を送信する方法です。
- 送信先アカウントが個人所有のものであるため、追跡が困難。
- 特に営業資料や顧客リストが送信対象となる。
クラウドストレージへのアップロード
Google DriveやDropboxなどの個人アカウントにデータをアップロードするケースがあります。
- アップロード後、データを別の端末でダウンロードできるため、検出が難しい。
- クラウドサービスは暗号化されている場合が多く、内容を把握しにくい。
スマートフォンのカメラで撮影
スマートフォンのカメラ機能を利用して、画面に表示されている機密情報を撮影する方法です。
- 外部接続を必要としないため、痕跡が残りにくい。
- ファイル転送アプリを使用して、無線でデータを送信するケースもある。
アクセス権限を悪用した不正アクセス
退職後も在職中に付与されたアカウントやアクセス権限を使い続けるケースがあります。
- 企業が退職時にアクセス権限を適切に削除していない場合に発生。
- メールアカウントやVPNを使用してデータにアクセスする。
以上のデータ持ち出しの手段は業務用端末のパソコンやスマートフォンを調査することで、持ち出しの事実を明らかにできます。
退職者の情報持ち出しの兆候
退職者による情報の不正な持ち出しは、本人が退職したあとに発覚することが多く、初期の兆候を見逃すと手遅れになることがあります。
特に近年では、データのコピーや送信がわずか数分で完了してしまうため、早期の異常検知と対応が重要です。
以下のような兆候が見られた場合は、情報持ち出しの可能性を真剣に疑うべきです。
| 退職者による情報持ち出しの兆候 | 解説 |
|---|---|
| 退職前後に大量のファイルコピーや移動履歴がある | 特にUSBメモリや外付けHDDなど外部記憶媒体へのコピーが急増しているケースが多い |
| 深夜・休日・最終出社日に集中したアクセス履歴 | 通常の勤務時間外のログインは、持ち出し準備の兆候である可能性がある |
| 個人メールアドレスへの送信履歴 | 社内ネットワークから個人のGmailやYahooメール宛に営業資料や顧客リストを送信 |
| クラウドストレージの利用が急増 | Google DriveやDropboxへのアップロード→外部端末でのダウンロードが可能になる |
| 退職後のVPN・社内システムへのアクセス履歴 | アカウント無効化が適切に行われていないと、不正アクセスが継続されるリスクがある |
| 業務端末の初期化・操作ログの削除 | 持ち出しの「証拠隠滅」が行われた可能性があり、後の調査が困難になる |
これらの情報持ち出しの兆候は、一見すると些細な行動に見えるかもしれません。
しかし、複数の兆候が重なった場合は明らかに異常信号であり、重大な情報漏洩につながる前触れであることが多いです。
兆候を見逃さず、速やかに内部調査・証拠保全・初動対応に着手することが、被害の最小化と法的対応の成否を分けます。
退職者による情報持ち出し発覚時の初動対応
退職者による情報持ち出しが発覚・疑われた際、企業が迅速かつ的確に対応できるかどうかが、被害の最小化と法的対処の成否を左右します。
以下では、発覚時に会社が取るべき初動対応の具体的な手順を、5つのステップに分けて解説します。
事実関係に関する社内調査の実施
まず最優先すべきは、事実関係の把握と社内調査の実施です。ここで対応を誤ると、情報持ち出しの証拠の喪失や被害の拡大を招く可能性があるため、調査は迅速かつ慎重に行う必要があります。
調査のポイント
- 誰が、いつ、どの情報を持ち出したのか特定する。
- 持ち出し手段(例:USBメモリ、メール、クラウドサービスなど)を特定する。
- どのファイルが調査対象で、どの程度の被害が出ているのかを定量的に評価する。
社内のログ管理ツールや社内のアクセス履歴、退職前後の操作ログなど、あらゆるデジタル証跡を収集することが基本です。
特に後述の法的措置に備えるためにも、調査記録は証拠性を意識して保全する必要があります。
情報持ち出しの証拠を確保する
調査結果を法的活用するためには、技術的証拠の確保が欠かせません。以下の対応を速やかに行いましょう。
具体的な対処法
- 退職者の業務端末(PC・スマホ)のログを保存・複製する
- USB接続履歴・ファイルアクセス履歴・メール送受信履歴などを取得
- 端末の初期化・削除操作が行われていないかを確認し、可能であればフォレンジック対応でクローン化。
証拠能力を維持した形での保全には、後述するフォレンジック調査の活用が極めて有効です。証拠の保全作業は専門技術が必要となるので、法的活用を見据える場合は証拠保全を外部のフォレンジック調査会社に依頼することを推奨します。
退職者への警告
違法な情報持ち出しが確認された場合、退職者に対して正式な警告を行うことが必要です。
内容証明郵便での警告
- 持ち出した情報の返還要求
- 情報の使用中止命令
- 今後の使用や漏洩があれば法的措置を講じる旨の通知
これらの通知は、証拠性が高い「内容証明郵便」で送付するのが基本です。
必要に応じて、弁護士の確認を受けて文面を作成することで、法的効力と説得力を担保できます。
関係者・転職先への連絡対応
データ漏洩の影響を受ける可能性のある関係者には、速やかに通知を行う必要があります。
通知対象者とその内容
- 顧客や取引先: 漏洩した情報の内容や対応策を説明する。
- 個人情報保護委員会: 個人情報が含まれる場合は、法的義務に従い報告する。
- 監督官庁/業界団体:業種ごとの規制やガイドラインに従い報告する。
対応の遅れや説明不足は、信用毀損・取引停止・報道リスクにつながるため、透明性と迅速性を重視しましょう。
法的措置の検討
状況によっては、民事的・刑事的措置を取ることで、被害を回復し、再発を抑止することができます。
民事的措置
- 損害賠償請求: 被害額に応じて適切な金額を請求する。
- 情報使用の差し止め請求: 持ち出された情報の利用停止を求める。
刑事的措置
- 不正競争防止法違反での刑事告訴: 企業の機密情報が不正に使用された場合に適用される。
- その他の関連法規: 状況に応じて法的手段を選択する。
法的措置を進める際は、専門の法律事務所に相談することをお勧めします。
退職者の情報持ち出し調査ならフォレンジック調査が有効
退職者の情報持ち出しにはUSBメモリや電子メールなどが使われることがあり、実態を把握しにくい傾向があります。悪質な場合、「社用パソコンのパスワードを勝手に変更する」「パソコンを初期化する」といった手口で証拠隠滅が行われるおそれもあります。退職者の情報持ち出し調査を実施する場合、端末の「フォレンジック調査」を実施することをおすすめします。
フォレンジック調査とは、PCやスマートフォン、記録媒体、ネットワーク機器などに残されたデジタル記録を解析し、事実関係を科学的に明らかにする調査手法です。「フォレンジック(forensic)」とは「法廷の」という意味を持ち、調査結果がそのまま裁判などで証拠として使用できるレベルで収集・解析されることが最大の特徴です。
日本でも、警察・捜査機関が犯罪立証に使用するほか、企業の内部不正や情報漏洩対応でも広く導入されています。
フォレンジック調査の結果が法的証拠として使える理由
デジタルデータは、改ざんや削除が容易である一方、証拠としての扱いには厳密な要件が求められます。フォレンジック調査では、以下のような工程で法的証拠性を担保します。
- 元データを変更せずに専用ツールで複製
- 操作ログやファイル履歴を改変不可な形式で記録・抽出
- データの出所や操作履歴を第三者的・中立な形式でレポート化
これにより、調査結果はそのまま民事訴訟・刑事告訴の証拠資料として正式に活用できるほか、警察への被害届提出や、社内処分・損害賠償請求の根拠としても有効な法的文書となります。
外部のフォレンジック調査会社に依頼する場合の注意点
フォレンジック調査を外部に依頼する際には、調査結果が裁判や社内処分の証拠として活用できるだけの“証拠性・信頼性”を担保できる会社を選ぶことが重要です。
特に以下の3点は、依頼前に必ず確認してください。
- 法的証拠保全に対応しているか(民事・刑事のいずれにも対応できる体制があるか)
- 調査対象デバイスに応じた実績と専用の設備を持っているか(PC/スマホ/サーバーなど)
- 作成される報告書が、公的機関・裁判所提出に耐えうる正式な文書形式か
また、調査のタイミングが遅れるほど、証拠は失われやすく、退職者側の証拠隠滅なども進んでしまいます。
証拠が改ざん・削除されてからでは、十分な調査結果とならない可能性があるので、退職者による情報持ち出しが疑わしい段階で速やかにフォレンジック調査会社に相談し、証拠保全などを行ってもらいましょう。
おすすめフォレンジック調査会社:デジタルデータフォレンジック
フォレンジック調査はまだまだ一般的に馴染みが薄く、どのような判断基準で依頼先を選定すればよいか分からない方も多いと思います。そこで、30社以上の会社から以下のポイントで厳選した、退職者の情報持ち出し調査が可能な編集部おすすめの調査会社を紹介します。
先述のポイントから厳選したおすすめのフォレンジック調査会社は、デジタルデータフォレンジックです。
デジタルデータフォレンジック

公式サイトデジタルデータフォレンジック
デジタルデータフォレンジックは、累計3万9千件以上の豊富な相談実績を持ち、全国各地の警察・捜査機関からの相談実績も395件以上ある国内有数のフォレンジック調査サービスです。
一般的なフォレンジック調査会社と比較して対応範囲が幅広く、法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで受け付けています。24時間365日の相談窓口があり、最短30分で無料のWeb打合せ可能とスピーディーに対応してくれるので、緊急時でも安心です。
運営元であるデジタルデータソリューション株式会社では14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスも展開しており、万が一必要なデータが暗号化・削除されている場合でも、高い技術力で復元できるという強みを持っています。調査・解析・復旧技術の高さから、何度もテレビや新聞などのメディアに取り上げられている優良企業です。
相談から見積りまで無料で対応してくれるので、フォレンジック調査の依頼が初めてという方もまずは気軽に相談してみることをおすすめします。
| 費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |
|---|---|
| 調査対象 | デジタル機器全般:PC/スマートフォン/サーバ/外付けHDD/USBメモリ/SDカード/タブレット 等 |
| サービス | ●サイバーインシデント調査: マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃調査、情報漏洩調査、ハッキング調査、不正アクセス(Webサイト改ざん)調査、サポート詐欺被害調査、Emotet感染調査 ●社内不正調査: 退職者の不正調査、情報持ち出し調査、横領・着服調査、労働問題調査、文書・データ改ざん調査、証拠データ復元 ●その他のサービス: パスワード解除、デジタル遺品調査、セキュリティ診断、ペネトレーションテスト(侵入テスト)、OSINT調査(ダークウェブ調査) 等 ※法人・個人問わず対応可能 |
| 特長 | ✔官公庁・法人・捜査機関への協力を含む、累計39,000件以上の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービス(※)を保有する企業が調査 ※第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2020年) |
| 基本情報 | 運営会社:デジタルデータソリューション株式会社 所在地:東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15階 |
| 受付時間 | 24時間365日 年中無休で営業(土日・祝日も対応可) ★最短30分でWeb打合せ(無料) |
退職者によるデー持ち出しを防ぐ対策
今後、退職者によるデータ持ち出しを防ぐためには、以下の対策を迅速に講じる必要があります。それぞれの対策について詳しく解説します。
ID情報の徹底管理
社内でID情報を徹底管理することで、誰が何をしているかといった行動履歴を取得することができます。退職者によるデータ持ち出しは、機密情報を個人で利用するクラウドストレージにアップロードすることで発生するケースもあるため、ID情報を管理しましょう。
機器の確保や情報のアクセス制限
ID情報の管理に加えて、退職予定者が使用している機器の確保や情報のアクセスを制限しましょう。退職する直前に、機器から重要なデータを抜き出したり外部へ転送する可能性があります。
また、データ持ち出しの証拠となり得るメールやアクセス履歴などを削除し、隠蔽することも考えられます。このような事態になる前に、退職予定者には顧客情報や機密情報へのアクセスを制限するなどして、事前の対策を行ってください。
ログの保存を実施する
ログの保存とは、社内ネットワークやシステムへのアクセス履歴を記録し、保存することを指します。これにより、誰がいつどのデータにアクセスしたかを追跡することができます。
具体的には、以下のようなログを保存することが推奨されます。
-
アクセスログ: ユーザーがシステムやデータにアクセスした履歴。
-
操作ログ: データの変更や削除などの操作履歴。
-
ネットワークログ: ネットワーク上での通信履歴。
これらのログを保存することで、退職者が不正にデータを持ち出した場合に、その事実を迅速に発見し、適切な対応を講じることができます。また、ログ分析ツールを活用することで、異常なアクセスパターンを自動的に検知することも可能です。
競業避止義務契約や秘密保持義務の締結
- 競業避止義務契約…退職後に一定期間、競合他社への転職や同業での起業・営業活動を制限する契約
- 秘密保持契約(NDA)…在職中および退職後も、業務上知り得た機密情報の漏えいや不正利用を禁じる契約
これらの契約は、データの持ち出しや漏えいを未然に防ぐ「動機の遮断」と「行動の抑制」の両面で有効です。たとえば、退職後に競合企業で自社の顧客情報や技術情報を使うことを目的にデータを持ち出すケースでは、競業避止義務がその転職や事業活動を制限し、そもそもの目的を成立させません。
また、秘密保持契約があれば、情報の不正使用自体が契約違反となるため、退職者に法的リスクを強く意識させ、行動の抑止につながります。さらに、万が一情報が外部に流出した場合でも、これらの契約があれば損害賠償請求などの法的対応が取りやすくなり、企業としての備えになります。
従業員の教育を行う
従業員に情報セキュリティの基本知識や、機密情報の適切な取り扱い方法を学ばせることで、業務中の情報漏洩リスクを減らすことができます。また、情報漏えいに関する社内規則を作成し、機密情報の取り扱い規則を徹底させましょう。
監視ソフトを導入する
データ持ち出しなどの不正行為を早期発見するには、社内データや端末を監視できるようなソフトの導入や環境作りを行ってください。
例えば社内端末に監視ソフトを導入することで、機密情報へのログインや業務と無関係なソフトウェアのインストールの有無などを製品によっては知ることができます。
まとめ
退職者による情報持ち出しは、どれほど信頼していた社員であっても、転職・不満・不注意といったさまざまな背景から発生するリスクです。
そして、その影響は信用失墜・損害賠償・訴訟と、企業経営に大きなダメージを与える可能性があります。
だからこそ、退職時点でのアクセス制御・ログ管理・契約整備といった「事前の仕組みづくり」に加え、万が一の際には「何が、いつ、誰によって持ち出されたのか」を可視化するための初動対応と証拠保全が不可欠です。もし少しでも不安を感じたら、証拠が残っているうちにフォレンジック調査会社へ相談してください。





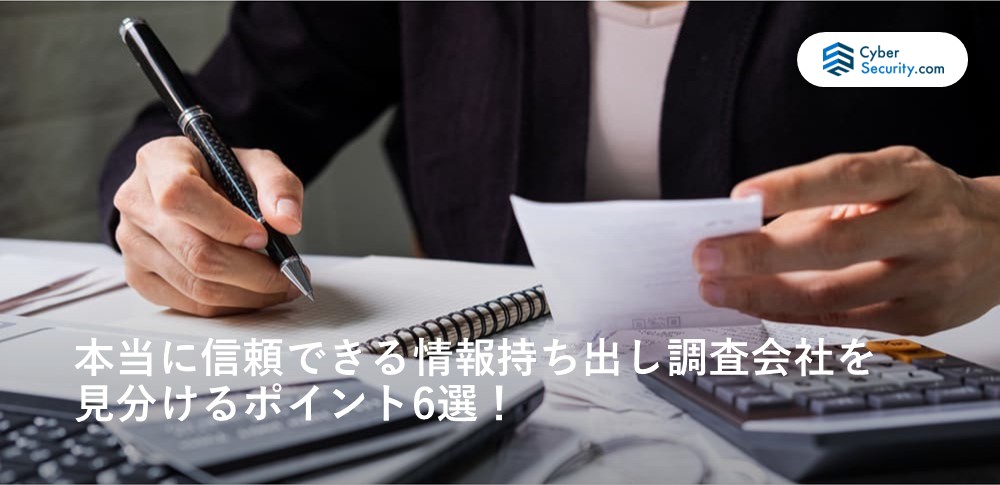





![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



