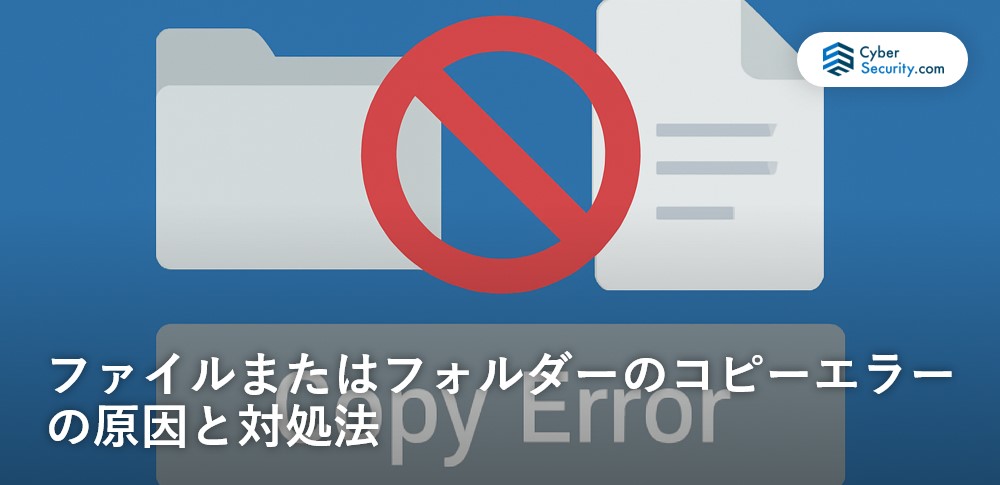
ファイルやフォルダーをコピーしようとした際に「エラーが発生しました」と表示されると、不安になりますよね。特に、大切なデータを移動したりバックアップしている最中に問題が起きると、作業が止まってしまい焦りを感じる方も多いはずです。
- コピー中に突然エラーメッセージが出て処理が止まる
- 特定のフォルダーだけコピーできない
- USBや外付けHDDに移動しようとすると失敗する
こうしたコピーエラーの背景には、ファイルシステムの破損やアクセス権限の問題、メディアや接続機器の不具合など、複数の原因が隠れています。放置するとデータの破損や保存先メディアの故障につながり、二度と取り戻せないリスクを招く可能性もあります。
本記事では、コピーエラーの代表的な原因と、初心者の方でも試せる具体的な対処法を解説します。トラブルを未然に防ぎ、安心してデータを守るために、ぜひ最後までご確認ください。
コピーエラーが発生する主な原因
コピーエラーにはさまざまな要因が考えられます。下記に代表的な原因をまとめました。
コピー先ドライブの容量不足
コピーしようとしているファイルのサイズが、保存先ドライブの空き容量を超えている場合、コピーは失敗します。特に動画やISOファイルなどの大容量データでは頻繁に起こるトラブルです。
リスク: 容量不足を放置すると、OSの動作不良やデータ破損につながる恐れがあります。十分な空き容量がない状態で作業を続けるのは危険です。
FAT32の4GB制限
USBメモリや外付けHDDがFAT32形式でフォーマットされている場合、1ファイルあたりのサイズ上限は約4GBです。それを超えるサイズのファイルはコピーできません。
リスク: 無理にコピーを繰り返すとファイルの断片化や破損が起こり、復旧が困難になることがあります。
書き込み保護または読み取り専用状態
USBメモリやSDカードには、書き込み防止スイッチがついているものがあります。これがオンになっている、あるいはファイル自体が「読み取り専用」に設定されていると、コピーできません。
リスク: 設定を無視して強制的に操作しようとすると、メディアが破損する可能性があります。
アクセス権限の不足・所有権の未設定
ファイルやフォルダに対して、現在のユーザーが「フルコントロール」や「書き込み」権限を持っていない場合、コピーできないことがあります。特に、他のPCやユーザーが作成したファイルで起こりがちです。
リスク: 無理に操作を行うと、アクセス権限を失いファイル自体が見えなくなる可能性もあります。
ファイルが他のソフトで使用中
ファイルが開かれていたり、クラウド同期中、バックアップ中など他のアプリケーションによって使用されていると、コピー操作はブロックされます。
リスク: 使用中のファイルを無理にコピー・移動すると、ファイルが壊れる可能性が高くなります。
ウイルスやマルウェアの影響
悪意のあるソフトウェアがファイルの操作を妨害している場合、コピー操作が途中で止まったり、アクセス自体がブロックされることがあります。
リスク: システム全体への感染や他のファイルへの被害拡大につながる恐れがあるため、放置は危険です。
リモート接続やネット越しの制限
リモートデスクトップ中やネットワーク経由でのコピーでは、セキュリティ設定や回線の制限が影響することがあります。転送が途中で中断されるケースもあります。
リスク: ネットワークや設定に不備がある状態での操作は、データの欠損や接続トラブルの原因になります。
物理障害・ファイルシステム障害
USBメモリや外付けHDD、SDカードなどの外部ストレージで、コピーエラーが頻発する、あるいは動作が極端に遅くなったと感じたことはありませんか?
こうした症状は、デバイス内部に不良セクタが発生している、あるいはファイルシステムが破損している兆候であることが多く、物理的な障害が進行している可能性があります。
動作が不安定なまま使い続けると、突然すべてのデータが読み込めなくなるといった重大なトラブルにつながる恐れがあります。とくに、カチカチと異音がする場合や、ストレージが認識されないといった症状は、物理障害が進行しているサインであり、早急な対応が求められます。
このような状態で自力対応を試みることは、状況をさらに悪化させるリスクを伴います。データが完全に消失する前に、信頼できる専門業者へ相談することが、安全かつ確実な選択です。
「とりあえず操作」は危険。自己判断がデータ消失を招くことも

機器に不具合が起きたとき、焦って自分で操作を試みた経験はありませんか?
一見すると単なるフリーズやエラーのようでも、内部では深刻な異常が進行している可能性があります。この状態で電源の再投入や設定変更を繰り返すと、システムが上書きされ、本来なら救えたはずのデータまでもが復旧困難になることがあります。
特に以下のような状況に当てはまる場合は、自己判断を避け、専門家による適切な診断を受けることが重要です。
- 絶対に失いたくない写真や書類が保存されている
- 大切な業務データが入っている
- 操作に自信がなく、何をすべきか迷っている
こうしたケースでは、早めの対応がデータを守る鍵になります。
そのため、まずは専門業者に相談し、正確な状態を見極めることが最善策といえます。
データ復旧業者を選ぶ際、「どこに相談すれば本当に安心できるのか」と悩む方は多いと思います。編集部では数多くのサービスを比較してきましたが、その中でも特に信頼性の高い選択肢としておすすめできるのが「デジタルデータリカバリー」です。
同社が選ばれている理由は、以下のような実績と体制にあります。
- 累計46万件以上の相談対応実績(2011年1月~)
- 15,000種類以上の障害事例への対応経験
- 復旧件数割合91.5%(内、完全復旧57.8%。2023年10月実績)
- 24時間365日対応のサポート体制
- 初期診断・見積りは完全無料
こうした数字は、単なる実績ではなく、「確かな技術」と「信頼に応える姿勢」の裏付けでもあります。
実際に、個人の大切な写真や法人の業務データまで、幅広いトラブルに迅速かつ的確に対応しています。
「何をすべきかわからない」「とにかく急いで対応したい」
そんなときは、まずは無料診断からはじめてみてください。正確な状況把握が、最善の一歩につながります。
コピーエラーへの対処法
原因に応じて、適切な対処を行うことで多くのコピーエラーは解決可能です。以下に具体的な手順を解説します。
空き容量とファイル形式の確認
コピー先のドライブに十分な空き容量があるかを確認し、必要であれば不要なファイルを削除してください。また、FAT32形式では4GBを超えるファイルは扱えません。
- エクスプローラーで対象ドライブを右クリックし「プロパティ」を選択。
- 「空き容量」と「ファイルシステム(FAT32/NTFSなど)」を確認。
- FAT32の場合は、必要に応じてデータをバックアップ後、NTFSにフォーマットを変更。
書き込み保護の解除
USBメモリやSDカードが書き込み保護(ロック)されている場合、コピーや移動が制限されます。この保護を解除することで操作が可能になります。
- 物理スイッチがある場合は「LOCK」から「UNLOCK」へ切り替え。
- エクスプローラーで該当ドライブを右クリック →「プロパティ」を開く。
- 「読み取り専用」にチェックが入っていれば外し、「適用」をクリック。
- レジストリで保護解除する場合:
– 「Windowsキー + R」で「regedit」と入力し、レジストリエディタを開く。
– 以下のパスへ移動:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
– 「WriteProtect」の値を「0」に設定。 - PCを再起動して設定を反映。
アクセス権限・所有権の取得
他ユーザーによって作成されたファイルやシステム領域のファイルでは、アクセス権限が不足していることがあります。フルコントロール権限を取得することで、コピーが可能になる場合があります。
- ファイルまたはフォルダーを右クリックし「プロパティ」を選択。
- 「セキュリティ」タブ →「詳細設定」をクリック。
- 「所有者の変更」→「自分のユーザー名」を選び、「OK」。
- 再び「セキュリティ」タブに戻り、「編集」ボタンをクリック。
- 自分のユーザー名を選び、「フルコントロール」にチェック →「適用」。
ファイル使用状況の確認とアプリ終了
ファイルがバックアップやクラウド同期中、または別のアプリケーションで開かれている場合、コピー操作がブロックされます。該当アプリを終了することで、操作が可能になります。
- ファイルを使用しているアプリ(例:Excel、Google Driveなど)をすべて終了。
- タスクバーを右クリックし「タスクマネージャー」を開く。
- 該当アプリケーションまたは「バックグラウンドプロセス」から該当ソフトを選び、「タスクの終了」をクリック。
- もう一度コピー操作を試す。
ディスクのエラーチェック
ドライブに論理エラーがあると、ファイルの読み書きに支障が出ることがあります。Windows標準機能でエラーチェックを実行して、修復できる可能性があります。
- エクスプローラーで該当ドライブを右クリックし「プロパティ」を選択。
- 「ツール」タブを開き、「エラーチェック」項目の「チェック」ボタンをクリック。
- エラースキャンが開始され、自動的に修復される場合もあります。
- 修復後、PCを再起動して再度コピーを試みる。
ウイルススキャンとシステム修復
ウイルスやマルウェアによって、ファイルの操作が妨げられるケースがあります。セキュリティソフトによるスキャンと、Windowsのシステムファイルチェックを実施することが有効です。
- お使いのウイルス対策ソフトで「フルスキャン」を実行し、脅威が検出された場合は隔離または削除。
- 「Windowsキー + R」を押して「cmd」と入力 → 右クリックで「管理者として実行」。
- コマンドプロンプトで以下を入力:
sfc /scannow - システムファイルの検査と修復が自動で行われます。
- 完了後、PCを再起動してコピーを再実施。
物理障害時は専門業者へ相談
ディスクの異音、頻繁なフリーズ、接続しても認識されないなどの症状がある場合、物理障害の可能性が高くなります。このような場合、自力での操作はさらなる損傷を招く危険があるため、早急にデータ復旧業者への相談をおすすめします。
- すぐにデバイスの使用を停止する。
- 通電や接続を繰り返さない。
- 信頼できるデータ復旧業者に症状を伝えて相談。
- 初期診断無料の業者を利用すると安心。
おすすめデータ復旧サービス・製品
物理的な損傷やソフトウェアで復元が難しい場合、以下のデータ復旧業者をご検討ください。
デジタルデータリカバリー
 公式HPデジタルデータリカバリー デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。 この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。
公式HPデジタルデータリカバリー デジタルデータリカバリーは、14年連続データ復旧国内売り上げNo.1(※1)のデータ復旧専門業者です。一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。 この業者は、相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際は、自力で復旧作業に取り掛かる前に、まずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。
| 対応製品 | ■記憶媒体全般 ハードディスク、外付けHDD、NAS/サーバー(RAID構成対応)、パソコン(ノートPC/デスクトップPC)、SSD、レコーダー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、スマホ(iPhone/Android)、ドライブレコーダー等 |
|---|---|
| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |
| 設備 | 復旧ラボの見学OK クリーンルームクラス100あり 交換用HDD7,000台以上 |
| 特長 | ✔データ復旧専門業者 14年連続データ復旧国内売上No.1(※1) ✔一部復旧を含む復旧件数割合91.5%(※2)の非常に高い技術力 ✔官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 ✔相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) ✔365日年中無休で復旧対応 |
| 所在地 | 本社:東京都六本木 持込み拠点:横浜、名古屋、大阪、福岡 |
デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ
※1:第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2020年) ※2:2018年2月実績 復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数 (2017年12月~2021年12月の各月復旧率の最高値)
まとめ
ファイルやフォルダーのコピーエラーは、一見単純なようで、実際は多くの原因が絡んでいます。容量不足やファイル形式の制限、使用中のファイルなど、状況に応じて適切に対応することで多くの問題は解決可能です。
しかし、物理的な障害が疑われる場合は、無理な操作は控えて専門のデータ復旧業者に早めに相談することが、データを守る最善の方法です。特に仕事や思い出が詰まった大切なデータであれば、慎重な対応が必要です。
本記事の内容を参考に、原因を切り分けながら適切な対処を行ってください。


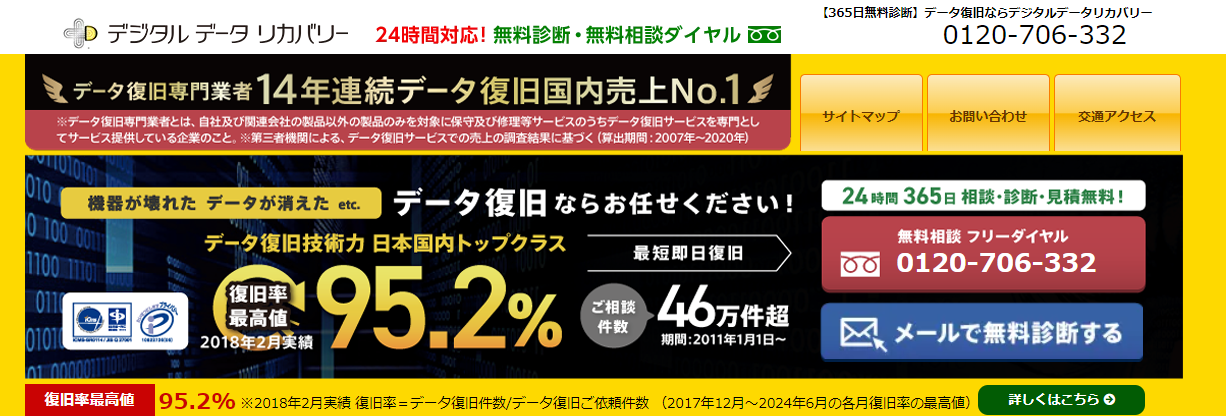
![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



