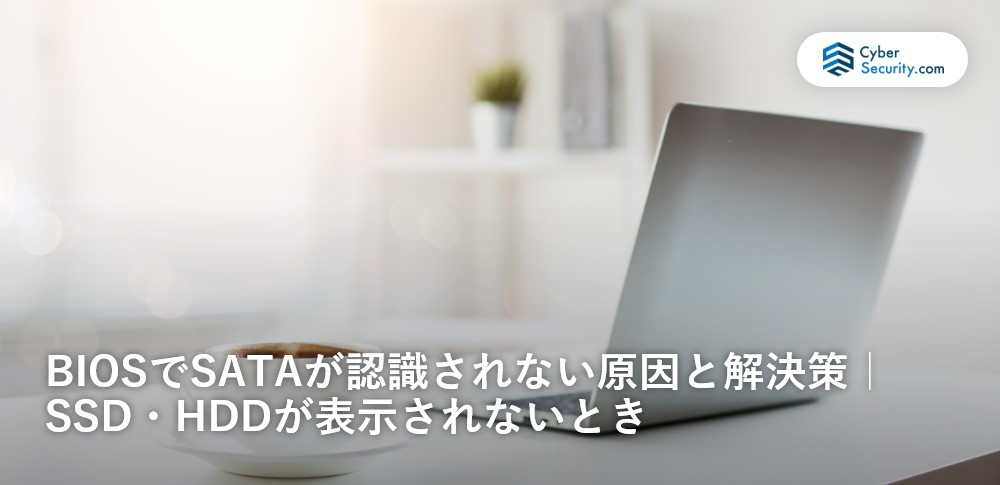
PCが起動しない、またはストレージが見つからないと表示されたとき、BIOS画面で確認するとSATAデバイス(SSDやHDD)が認識されていないことがあります。データを失う前に、原因を突き止めて正しく対処することが重要です。本記事では、BIOSでSATAが認識されないときの原因と解決法を徹底解説します。
SATAが認識されない原因
BIOSでSSDやHDDが認識されない場合、以下のような原因が考えられます。
ケーブルの問題
ストレージデバイスがBIOSに表示されない場合、まず疑うべきなのが接続ケーブルのトラブルです。SATAケーブルや電源ケーブルがきちんと接続されていなかったり、内部で断線や劣化が生じていたりすると、BIOSがストレージを正しく認識できません。特に、長期間使用しているパソコンでは、ケーブルの抜き差しや経年劣化によってコネクタが緩んでいたり、接点が酸化して接触不良を起こしているケースもあります。別の正常なケーブルやポートを使って接続し直すことで、問題が解決することもあります。
BIOS設定の不備
BIOS(UEFI)の設定が適切でない場合も、ストレージが認識されない原因になります。たとえば、SATAコントローラー自体が無効になっていたり、「IDE」「AHCI」「RAID」といったSATA動作モードが正しく設定されていないと、ストレージが表示されないことがあります。
加えて、近年のPCでは「Secure Boot」や「CSM(互換サポートモジュール)」といった設定項目が影響する場合もあります。特に、古いOSやレガシーデバイスを使用していると、CSMの有効化が必要なケースもあるため、環境に応じた設定確認が重要です。
ドライバーやファームウェアの問題
ハードウェアが物理的に正常でも、ソフトウェア側の不備によって認識されないケースがあります。古いBIOSバージョンや、チップセット・ストレージコントローラーのドライバーが更新されていないと、接続されたSSDやHDDを正しく認識できないことがあります。
特にNVMe接続の最新SSDでは、古いマザーボードとの互換性に問題が出やすいため、製造元から最新のBIOSやドライバーをダウンロードして更新することが重要です。ファームウェアの更新も、認識不良の改善につながることがあります。
ポートやデバイスの競合
マザーボードの設計上、特定のポート同士が排他仕様になっていることがあります。たとえば、M.2スロットにSSDを装着すると、一部のSATAポートが自動的に無効化される仕様の製品が存在します。これを知らずにSATAデバイスを接続しても、BIOS上では認識されず「壊れている」と誤解してしまうことがあります。
また、複数のストレージを同時に使用している場合や、外部デバイスとの接続状況によって競合が発生し、一部のデバイスが検出されない場合もあります。マザーボードのマニュアルを確認し、ポートの使用制限や優先順位について把握しておくことが重要です。
ハードウェアの不良
SSDやHDDそのものに不具合がある、あるいはマザーボード側のSATAポートに物理的な故障があると、デバイスは検出されません。こうした問題はハードウェア診断で特定が可能ですが、自己判断での分解や部品交換は非常に危険です。誤った操作を行うことで、内部データがさらに破損する恐れがあり、最悪の場合は復旧の可能性が大きく下がってしまいます。
そのため、正確な原因の特定と安全な対処を行うためには、専門的な知識と設備が必要です。特に物理的な障害が疑われる場合には、デバイスを無理に起動させず、速やかに専門業者へ相談することが重要です。
SATAが認識されないときの解決策
以下の対処法を順番に実行することで、BIOSでSATAが認識されない問題を解消できる可能性があります。
基本的な接続確認
まずはケーブルやポートなど、物理的な接続状況を確認しましょう。
- 電源ケーブルとSATAケーブルを一度抜き差しして、しっかり接続されているか確認します。
- 可能であれば、新しいケーブルに交換してみてください。
- 別のSATAポートに接続して、ポート側の不良を切り分けます。
BIOS設定の確認・変更
ストレージデバイスが正しく認識されるよう、BIOS内のSATA設定を見直しましょう。
- PC起動時に「F2」や「Delete」キーを押してBIOSに入ります。
- 「SATA Configuration」項目でSATAコントローラーが「Enabled」になっているか確認します。
- モードが「AHCI」になっていることを確認します(IDEになっている場合は変更)。
- 「CSM」や「Secure Boot」の設定を変更して再起動します。
- 設定に問題がある場合、「F5」キーで初期化し、「F10」で保存して終了します。
ドライバーとファームウェアの更新
OSやBIOSが古いままだと、新しいストレージデバイスが認識されない場合があります。
- 別のPCを使用して、マザーボードメーカーの公式サイトから最新のBIOSとチップセットドライバーをダウンロードします。
- USBメモリに保存し、問題のPCに接続します。
- BIOSから「EZ Flash」などの機能を使ってアップデートを行います。
- Windows起動後は、「デバイスマネージャー」からストレージ関連のドライバーも更新します。
接続デバイスの競合を解消
他のストレージやUSB機器が原因で、SATAデバイスが認識されていない場合があります。
- 外付けHDD、USBメモリ、SDカードなど、すべての外部ストレージを取り外します。
- SATA接続のSSDまたはHDDのみを接続してPCを起動します。
- BIOSで対象デバイスが表示されるか確認します。
ハードウェア診断を行う
デバイスそのものやマザーボード側の故障を確認するために、ハードウェア診断を行います。
- 問題のあるSSD/HDDを、別のPCに接続して動作確認します。
- 別のストレージを問題のPCに接続し、認識されるか確認します。
- これにより、ストレージ側の故障かマザーボード側の故障かを切り分けます。
SATAが認識されないまま誤った操作を行うと、SSDやHDD内のデータが損傷するリスクがあります。以下の専門業者に相談すれば、安全かつ高精度でデータを復旧できる可能性が高まります。
おすすめデータ復旧サービス
データが必要な場合、技術力のある適切な業者の選定といっても、素人には判断が難しいです。
そこで、データ復旧サービス各社の価格、内容(対応製品)、期間や特長から比較した、おすすめのサービスを紹介します。
デジタルデータリカバリー
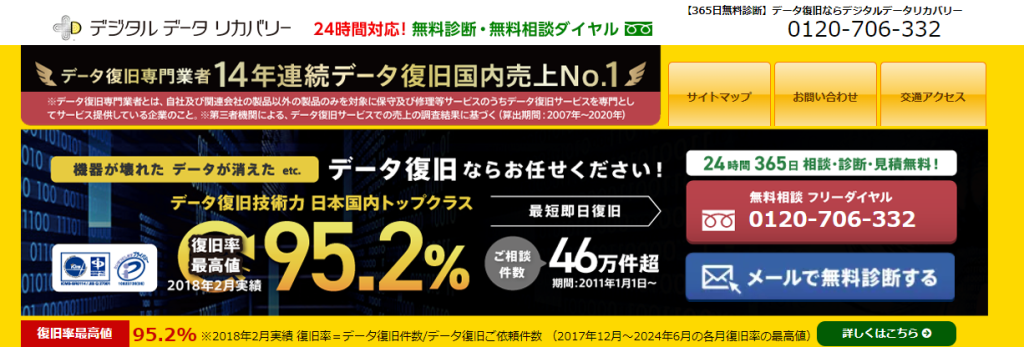
公式HPデジタルデータリカバリー
デジタルデータリカバリーは、データ復旧国内売り上げNo.1のデータ復旧専門業者です。復旧率最高値は95.2%と非常に高い技術力を有しています。依頼の8割を48時間以内に復旧と復旧のスピードも優れています。また、官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績があります。
相談から見積もりの提示まで無料で行っているため、データ復旧を検討している際はまずは最大手であるデジタルデータリカバリーに相談すると良いでしょう。
デジタルデータリカバリーの評判に関しては以下の記事で紹介しています。
| 復旧費用 | 相談から見積もりまで無料 500GB未満:5,000円〜 500GB以上:10,000円〜 1TB以上:20,000円〜 2TB以上:30,000円〜 |
|---|---|
| 対応製品 | RAID機器(NAS/サーバー)、パソコン(ノート/デスクトップ)、外付けHDD、SSD、USBメモリ、ビデオカメラ、SDカード・レコーダー等記憶媒体全般 |
| 復旧期間 | 最短当日に復旧完了(本社へ持ち込む場合) 約80%が48時間以内に復旧完了 |
| 特長 | 14年連続データ復旧国内売上No.1 復旧率最高値95.2%の非常に高い技術力 官公庁や大手企業を含む累積46万件以上の相談実績 相談・診断・見積り無料(デジタルデータリカバリーへの配送料も無料) |
デジタルデータリカバリーのさらに詳しい説明は公式サイトへ
データ復旧業者の料金形態は以下の記事で紹介しています。
まとめ
SATAデバイスが認識されないときは、まずケーブルの交換や別ポートへの差し替えを試しましょう。
それでもダメな場合は、BIOS設定のSATAモード(AHCI/IDE)を確認し、正しく設定されているかをチェックしてください。


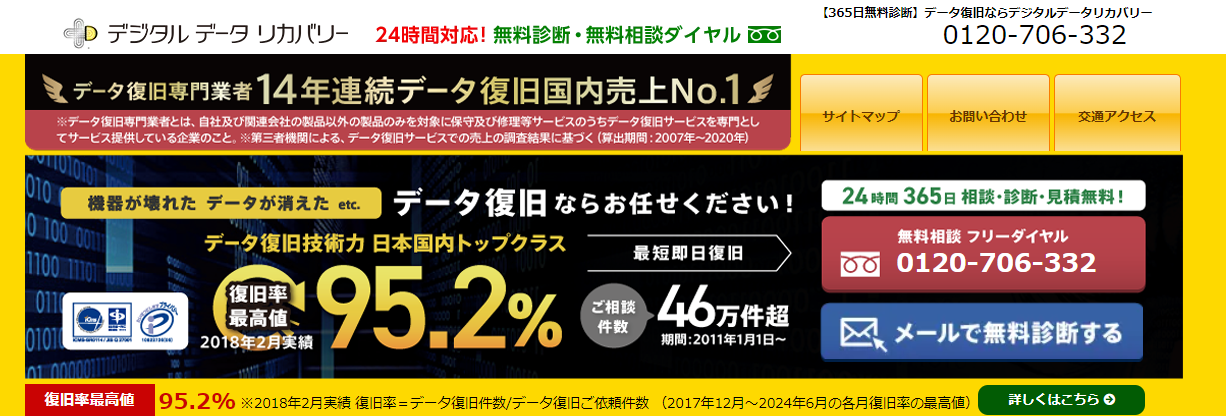
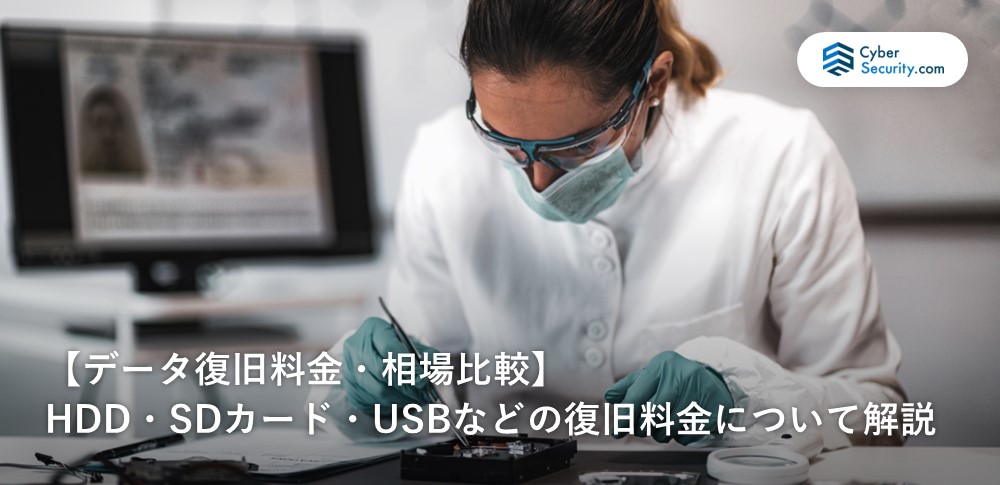
![中小企業の情報瀬キィリティ相談窓口[30分無料]](/wp-content/uploads/2023/07/bnr_footer04.png)



